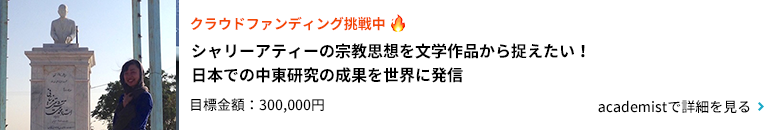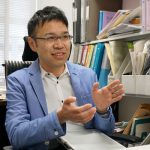宗教から読み解く”皮膚感覚”のイラン – 東京外国語大学・村山木乃実氏
イランという名前を聞いたとき、なにを思い浮かべるだろうか。中東の経済大国、反米、シーア派、核開発……。いずれもニュースでよく目にする言葉だ。しかし、それらの言葉では掴みきれていない「イラン」があるのではないか。文学や宗教学の観点からそうしたイランの等身大の姿に迫ろうと研究するのが、東京外国語大学の村山木乃実氏だ。村山氏が研究するイランの思想家アリー・シャリーアティーは複雑な歴史を背負ったイランを凝縮した存在であるという。一人の思想家を通してイランという国を知ることの魅力について村山氏にお話を伺った。

——村山さんがイランに興味を持ったのははじめてイランを訪問したときに感じた驚きにあったとクラウドファンティングのプロジェクトページで知りました。
私にとって初めてのイランは、学部2年生のとき、研修と旅行で1か月くらいイランを廻ったことでした。それまではイランというと、「反アメリカ」とか、「ちょっと怖い」など、漠然と危ないというイメージがあったのですが、実際に行ってみるとまったくそんなことはありませんでした。人々も温かく、国教も違うのに親近感を感じたんです。自分がそれまでに持っていたイランのイメージとのギャップに驚きました。またイランの人たちは、今も国教になっているイスラームのシーア派要素だけでなく、イランがイスラーム化する以前のイラン文化的な精神性も持っていることを肌身で感じました。こうしたイラン文化の多面性も、イランに魅かれた点のひとつですね。
——それでイランに興味を持って帰国したあと、シャリーアティーにはどのように出会ったのですか?
帰国して、まずは今のイランがどのようにしてできたのかより詳しく知りたいと思い、今のイランが誕生するきっかけとなった、1979年のイラン・イスラーム革命についての文献を読み漁りました。文献を読むと、ホメイニーという宗教指導者が頂点に立って革命が成就するという内容は、よく書かれていました。またそのなかで、革命のイデオローグとしてもう一人よく引用されるのがシャリーアティーでした。彼は一体何者だと思っていたときに、ちょうどシャリーアティーの一番有名な著作の一部の翻訳『イスラーム再構築の思想 – 新たな社会へのまなざし』(桜井秀子訳、大村書店)を見つけて読んだのが、シャリーアティーとの出会いですね。

——村山さんの研究についてお聞きする前に、従来の研究ではシャリーアティーはどのように扱われていたのか教えてください。
従来はシャリーアティーの思想のみに注目する研究はあまりなく、結局は「革命のイデオローグ」としての文脈や、社会におけるシャリーアティーのインパクトなどのテーマに付随する形で語られることが多かったですね。こうしたテーマについては、イラン・イスラーム革命研究のなかで1980年代に世界中で取り上げられました。
ただ、こうした研究の資料とされるのが、ほとんどが講演の書き起こしを元にしたもので、全部で36巻ある全集のうちのほんの一部でしかなかったんです。私はそれ以外の著作、そのなかでもシャリーアティー思想研究で取り上げられてこなかった彼の文学作品を読解することで、シャリーアティーの思想を再評価しようと思っています。
——どちらかというと政治思想の文脈の研究が多かったのですね。それにしても、なぜシャリーアティーがイランでそれほどまでの影響を持ちえたのでしょうか?
シャリーアティーが活躍する時代には、「上からの西欧化」を進めるパフラヴィー朝政権、それに抗う社会主義者や伝統的な知識階級であるウラマーなどがひしめき、価値観が乱立していました。特に若者にとっては、どこに自分たちの足を置いてよいかわからない混沌とした状態が続いていたんです。そのなかでシャリーアティーは、イラン人たちにとってわかりやすい言葉で、イランの文化的な支柱として日常のなかに染み付いている文学、古典詩、リズミカルな言葉、イラン人なら誰が聞いてもわかる説話などを織り交ぜて自分たちのアイデンティティはシーア派にあると主張しました。これが、大衆に響いたのだと思います。彼の講演の録音がたくさんあるのですが、非常にイランの人々の心を突き動かすものだったことがわかります。たとえば、ネイティブの先生も「これは泣いてしまう」と仰っていました。
——当時の人はどこでシャリーアティーの言葉を聞くことができたんですか?
シャリーアティーが有名になるのは1960年代後半ですが、彼は1950年代くらいから地元のラジオでペルシア文学の番組を持っていました。同じくらいの時期に地元の地方紙でコラムを執筆したり、そのあと留学でフランスへ行ってからも雑誌を作ったりするなど積極的に自分の思想を発信していました。さらに帰国して母校である地元の大学で授業を持つのですが、その授業が地元のおじちゃんやおばちゃんといった学生以外の人も来るくらい人気を博し、彼がテヘランに移ったあともその人気は途絶えませんでした。

——彼は思想家というだけでなく、メディアの扱いも上手かったんですね。村山さんの研究ではシャリーアティーの「もうひとつの顔」である神秘主義的な側面に迫っていますね。
神秘主義そのものは、端的には神と直接的につながる行為を意味しています。イスラーム教の歴史のなかでは宗教と政権が結びつくことに反発する形で、「それはムハンマドが言っていたようなイスラームではなく、自分たちは世俗化した現世を捨てて、神と直接繋がるのだ」というひたすら神を思う禁欲主義的な立場が隆盛してきます。神に至る修養として整理、確立されてきたものが、神との合一を実現するための道、すなわち「神秘主義」と言われるようになったと考えられています。導師と弟子との関係に基づく修養の方法が構築されてきて、従来の禁欲主義が神秘主義と呼ばれるようになったのですね。さらに、神秘主義をペルシア詩で表現した「ペルシア神秘主義」はイランの文学史のなかでも、宮廷文化から生まれたペルシア詩が神秘主義と融合して、とても美しく思想的なものも表現できるようになった点で重要視されています。シャリーアティーもこのペルシア神秘主義にかなり影響を受けています。
——どういった点にその影響が見え隠れしますか?
それは、彼が無意識のなかで書くという方法を大事にしている点からも伺えます。講演の内容は基本的にある聴衆のことを頭に置きながら考えると思いますが、彼は自分に向けて自分の思いのままに書いていくんですよね。たとえばある文章では、日々の描写から入っていくシーンから、突然、この世の世界ではない世界に入っていて、そこに神秘主義的な世界観や言葉が多く使われています。さらに調べると、これはイランの中世の神秘家で当時異端視されていた、アイヌル・クザート・ハマダーニーという人の影響を色濃く受けたものだということが明らかになりました。シャリーアティー自身の考えがイスラームだけではなくて、たとえばイスラーム以前のイランだったり、あとは西欧思想だったりと複雑に絡み合っているのです。それらを丁寧に読み解いていったときに、ひとつに繋がる瞬間があるんですよ。研究をしていて、一番楽しい瞬間でもありますね。
——村山さんは、「イラン研究学生機構」や「ペルシア語文学会通信」を立ち上げるなど、研究のコミュニティを築くことにも積極的ですね。
「イラン研究学生機構」は、東京外国語大の学生と有志が立ち上げた団体です。私は大学院から東京外国語大にきたのですが、東京外国語大では学部1年生から必修でペルシア語をたくさん勉強することもあって、イランについて自分で知る余裕もないままお腹いっぱいになってしまっている人が多いことを知り、心を痛め、自分たちでもっとイランを学べるきっかけがあればよいのではと考えていました。それで何人かに声をかけて、自分たちで好きに調べて、まとめて、アウトプットできる機会があればよいのではと思い、団体を立ち上げて雑誌を作ったんです。
「ペルシア語文学会通信」の方は、もともと今から10年くらい前に私の先生の研究室に所属していた院生の方々が有志で作っていたものです。私が大学院に入ったときは休刊していたのですが、今年復刊させました。博士課程に進んで投稿論文を書くとなったときに、ペルシア文学を研究している先生自体が日本に少ないこともあり、査読が通りづらいことに問題意識を感じて、「だったら自分たちで発信の場を作っちゃえば良いのでは?」と思って作ったのが復刊のきっかけです。

——村山さんのメディア製作の上手さはシャリーアティーと重なって見えてしまいます……。最後に、ペルシア文学や宗教学的な観点でイランの文化を理解することの魅力について聞かせてください。
イランの場合は、文学作品なり知識人の思想なり、ほとんどの事象がシーア派の衣を纏って表出してくるんですよ。やはり、イランを知るにあたってはイスラーム、シーア派を避けて通ることができないという点で、現代のイランを知るには宗教が一番大切ではないかと思っています。さらに、シーア派と言ってもイランの場合、非常にイランの土地に根付いたシーア派です。それを紐解いて読み解いて行くことは、宗教学だからこそできるものだと思います。結局、宗教を理解することは現実世界の表面に現れたイランの人々の生活の様式だとか、当たり前だと思っている彼らの「皮膚感覚」を理解するためのひとつの鍵となるので、それを手にすることができることが、この学問の魅力ですね。

村山木乃実氏プロフィール
東京外国語大学大学院総合国際学研究科言語文化専攻2年。松尾金蔵記念奨学基金奨学生。中央大学総合文化政策学部卒業。修士課程より東京外国語大学大学院に入学し、
イランの現代宗教思想についてペルシア文学・ 宗教学の観点から研究している。
この記事を書いた人

- 東京大学大学院学際情報学府修士課程。学部では1年次から哲学の原書テクストを精読するゼミに参加し鍛えられ、ベルクソン哲学で卒論を執筆。現在は人文社会科学がどこから来てどこへ向かうのかについて関心があり、特にそれと社会との交差点であるメディアに照準を定めて研究を進めている。