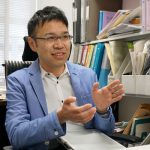「分析哲学」の使命は”論理の明晰化”にあり – 『フィルカル』編集長・長田怜氏
分析哲学という分野をご存知だろうか。アメリカやイギリスなどの英米圏では、哲学といえば分析哲学のことを指すほどメジャーな分野になっている。日本でも研究が盛んに行われており、3年前には若い世代の研究者が中心となり「分析哲学と文化をつなぐ」をコンセプトとした『フィルカル』という雑誌も創刊された。編集長を務める長田怜氏に、分析哲学とは一般的に思い浮かべる哲学とはどのように違うのか、『フィルカル』とはどのような雑誌なのか、お話を伺った。

分析哲学ってどんな学問?
——まずはじめに分析哲学とはどんな分野か、他の哲学との違いについて教えてください。
おそらく、日本人が思い描く哲学者のイメージというのはドイツやフランスの「大陸哲学」の哲学者だと思います。ハイデガーやデリダなどの大家の哲学者がたくさんいて、彼らが主張していることを丹念に読み解くのが哲学であるというイメージを抱いている方は多いのではないでしょうか。それに対して分析哲学では、過去の哲学者というより、トピックを単位に研究しています。
たとえば、「因果関係とは何か」、つまり、「ある物事が別の物事の原因となるとはどういうことか」というトピックがあるとします。このトピックに対しては、物事には何か因果的な力みたいなものが実在していてそれが作用する、と考える立場もあれば、そのようなものは実在しなくてもよいという立場もあります。こうした複数の立場のあいだで議論し、論理的に批判しあうようなロジカルなプロセスが、いかにも分析哲学っぽいと言えます。
——具体的にはどういったプロセスで研究を進められるのでしょうか。
哲学的な概念の規定をめぐって批判的に議論する、というのはよく行われることです。先ほど例に挙げた「因果関係」という概念を規定したいとしましょう。このとき、あらゆる因果関係のケースを含み尽くすように因果関係の特徴づけをしていく必要があります。
より具体的には、因果関係を「反事実条件文」で規定するという立場があります。たとえば、「私が石を投げたから花瓶が割れた」という因果関係の文を、反事実条件文で言い換えると、「私が石を投げなかったら、花瓶は割れなかっただろう」という文になります。原因を取り除くと結果も生じないという仕方で定式化できる関係が因果関係だという主張です。これは、因果的な力みたいなものが実在していると想定しなくても言える点で抑制的な主張です。
しかし、ちょうど同時に別の人が石を投げていて、その石は私の石よりほんの少し遅く花瓶にぶつかるはずだった、というような場合を考えましょう。すると、私が投げなくてもその花瓶が割れることがありうるわけです。この例は、反事実条件文では必ずしも因果関係を特定できたことにはならない、という批判に使えます。私が石を投げたことは明らかに花瓶が割れた原因であるのに、反事実条件文のほうは成り立たなくなってしまうからです。このように、一度定式化されたものに反例が出されて、修正して答える、といったプロセスが分析哲学では一般的です。
——因果関係などの概念をかなり細かく分析していくのですね。分析哲学はどういった経緯で成立してきた学問なのでしょうか。
19世紀までには自然科学が制度化され、さまざまな領域に力を示していきます。そのときに、人文学や社会科学の学問分野ではどういった方法で研究していけばよいか盛んに議論されました。ドイツ語圏では、人文学には人文学独自の方法があると主張する立場があり、たとえばハイデガーなどの哲学者はこれに含まれます。
それに対して、自然科学の方法で哲学もうまくいくと主張したのが論理実証主義の人たちでした。彼らは「哲学を科学化する」と主張して、哲学の内容の論理的な明晰化に使命感を持っていました。この論理実証主義が分析哲学のひとつの源流になっています。哲学の方法論に関するこうした論争を背景にして分析哲学は成立してきました。もちろん、これはかなり単純化した見方で、論理実証主義以外にイギリスやアメリカには独自の流れもあり、最近はそうした複雑な事情も含めて、分析哲学の成立に関する歴史的研究が盛んに行われています。

客観的な認識に到達するための論理体系
——長田さんはどのような研究に取り組まれていますか。
ルドルフ・カルナップ(1891-1970)という論理実証主義の一番代表的な哲学者について研究しています。論理実証主義は今まで、「有意味な言葉遣いは最終的には観察、つまり私たちがデータを取ってくるような場面に落とし込めるのだが、ヘーゲルなどの哲学者は、そこに落とし込めないことしか語っていないから無意味なのだ」と主張する立場として捉えられてきました。このような立場は、これまではイギリス経験論と似ていると考えられてきました。つまり、心理的に湧いてくる感覚的なデータこそが認識の最初の素材で確実なものであり、そこからできあがってくる「これが机である」や「これは木でできている」という認識については懐疑的、もしくは最初の素材にしっかり関連づけられない限り確実ではない、とする立場だとみなされてきたのです。
しかし、1980年代以降、論理実証主義者をもっと歴史的な文脈に引き戻して考えようという流れが出てきました。論理実証主義者はドイツやオーストリアなどドイツ語圏の人たちでしたので、イギリス経験論というよりはどちらかというとドイツのカント哲学の影響を強く受けているんですね。カント哲学は、私たちの認識の素材が主観的であるにも関わらず、いかにして客観的な認識に到達できるか、を重要なテーマとしていました。カルナップ哲学もカント哲学とテーマを共有していると考え、彼のテキストを読解しました。
——哲学とはいえ歴史的なアプローチによってわかることもあるのですね。では、どうすれば客観的な認識に到達することができるのでしょうか。
論理実証主義の文脈では論理学を用います。カルナップは1928年に出した『世界の論理的構築』という本のなかで、主観的な体験から客観的な認識にどのように到達するかを論理学的に解明するという仕事をしました。私はその本について研究し、博士論文を書きました。
これまでの話は認識論についてですが、哲学には存在論というジャンルもあります。イギリス経験論的な理解だと、出発点の感覚的なデータは存在していますが、そのあと認識されるものの存在については懐疑的だったり、副次的だとみなされたりします。これは反実在論という立場です。カルナップも反実在論者として捉えられてきたのですが、そうではなく、存在論的にもどちらかというと実在論の立場であると私は考えました。彼は存在を前提として、その認識への到達を示す手段として論理体系をつくった、存在とその存在を認識する手段を分けて考えることができる、というのが、私が博士論文で主張したかったことです。
——長田さんはいつ頃から分析哲学の研究の道に進もうと思われたのですか。
今から振り返ると単純化される可能性があるんですが……。もともと、高校生の頃から哲学的な事柄に関心はありました。高校時代に書いていた日記を読み返すと、「旅行に行きたい」といったような内容を書いたある日を境に記述が途絶え、次に書かれていたのが半年後で、急に「絶対的な真理とは何か」などと書いてありました(笑)。その頃から、「どうしてある事柄を確実に真理だと言えるんだろう」といったような哲学的なことを考えていたと思います。
ただ、一番の転機は分析哲学の大御所である飯田隆先生が書かれた『言語哲学大全I』(勁草書房)という4巻本シリーズの第1作を読んだときだったと思います。哲学でもちゃんと論理的なステップを踏んで説明できることを知り、衝撃を受けました。それから、分析哲学を研究したいと思うようになりました。ですので、良い本との出会いや優れた研究者に触れることはとても大事だと思っています。
『フィルカル』の編集長として
——良い本というと、分析哲学の研究者が編集委員となって制作している『フィルカル』という雑誌で、長田さんは編集長としてもご活躍されています。『フィルカル』はどのような雑誌ですか。
もちろん、良い哲学を知ってもらいたいということも雑誌の意図のひとつですが、雑誌のコンセプトとしては「分析哲学と文化をつなぐ」ということを掲げています。とりわけ、分析哲学は概念を精緻化していく作業をしがちです。そうすると、一般の人にはなかなか馴染みにくくなります。しかし、いくつかの背景もあり、分析哲学の界隈で閉じずに、ハイカルチャーやポピュラーカルチャーといった狭い意味での文化と分析哲学をつなげるような試みができそうだなという気配を感じ、この雑誌を創刊することにしました。

——いくつかの背景とは何でしょうか?
まずひとつは「分析美学」という分野の研究者が日本でも若い世代で増えてきたことです。分析美学は美学の話題を分析哲学の方法で研究する分野で、60~70年くらいの歴史を持っており、この雑誌にとっての背骨となるようなジャンルです。美学なので、「ビデオゲームとは何か」とか、「アニメの絵は小説の言葉と何が違うか」といった問いを立てて、文化現象を分析哲学の方法で理論的に定式化することに取り組みやすいのです。日本でもアカデミックに文化を分析できる専門家が出てきたことが背景のひとつです。
また海外でポピュラーカルチャーを哲学者が論じた本がたくさん出ていたことももうひとつの背景でした。たとえば、『マトリックス』や『サウスパーク』などの映画や、「メタリカ」というヘヴィメタル・バンドなどのポピュラーカルチャーについて哲学者が論じるようなシリーズが出ていたりするんですね。オープンコート出版社などが代表的です。日本でも似たことができるのではと思ったことが、ふたつめの背景です。
——『マトリックス』を哲学者が論じたらどうなるか、馴染みがあるテーマということもあり確かに気になります。雑誌では、分析哲学それ自体もひとつの文化現象として考えられると書いてありました。こちらについても教えてください。
今述べた話は、文化を分析哲学で分析するという場合ですが、分析哲学もひとつの文化現象として見ることができると思っています。論理実証主義の歴史的な研究が進み、モダニズム芸術に大きな影響を与えたバウハウスというドイツの学校へ、カルナップが講演に行っていたこともわかってきました。彼がそこに行ったのは当時の建築運動と彼の研究の理念が何か共振したからだと思います。『フィルカル』の創刊号でも書きましたが、モダニズムと呼ばれるような思想運動の一環としてドイツ語圏の科学哲学が出てきたとも考えられます。このように、ある種の広い文化のなかで分析哲学を位置付けることもできるのではと思っており、それに関連した記事も掲載しています。
——編集部には分析哲学の若い研究者の方が多いこともこの雑誌のユニークな点だと思います。編集部はどういった雰囲気ですか?
みんなノリノリです。編集に協力してくれる研究者のみなさんは、自分たちの研究を外に向かってアピールすることに共感してくれています。編集委員に入っていただいている先生たちもこの雑誌を盛り上げてくれています。また、大学などに属さず、普通に会社に勤める在野の研究者も多く協力してくれていて、ものすごくきちんとした論考を寄稿してくれています。おそらく、昔だったらいなかったような背景を持った人たちが協力してくれているのも、この雑誌の特徴のひとつですね。
——最後に『フィルカル』の編集長として、そしてひとりの研究者として今後の抱負を教えてください。
『フィルカル』はまだおそらく研究者とその周辺の人が主な読者となっています。今後の課題は浅い広がりの入り口にいるような人にも分析哲学の魅力を知ってもらうことです。また、今はアニメやマンガなどの分析が多いのですが、そのように文化などを分析するための哲学内外の方法論、たとえば社会科学の方法論などについても、社会科学者などと協働して取り上げたいと思っています。先ほどお話ししたように、こうした科学方法論の話は、分析哲学の出自に関わる話であると同時に、社会科学の成立と展開に関わる話、さらには、そうした広い文脈における文化としての分析哲学に関する話でもあります。
——研究者としては今後どのような研究に取り組まれたいですか。
博論では初期のカルナップの研究をしましたが、今後はカルナップの晩年に到るまで研究を広げていきたいと思っています。というのも、彼は晩年、帰納論理について研究していました。普通、論理学と聞いてイメージされるのは前提から結論が必ず出てくる演繹論理です。それに対して、帰納論理というのは前提から帰結は「ある程度だけ」言えるというものです。すると、先ほど述べた社会科学の話にもつながっています。たとえば、統計を用いて科学的な研究をする際に採用する統計モデルと帰納論理のシステムを対応させるようなことができるのではと思っています。
ですので、先ほどのフィルカルの今後の展開としての述べた社会科学の話は、フィルカルとしてだけではなく、私自身の関心でもあります。編集長として、そしてひとりの研究者として、科学方法論はどうあるべきかといったような大きな話について探求を続けていきたいと思います。

長田怜氏プロフィール
慶應義塾大学、横浜国立大学など非常勤講師。「分析哲学と文化をつなぐ」雑誌『フィルカル』編集長。1977年静岡県生まれ。1996年に東京大学文科III類に入学後、同大学文学部思想文化学科卒業。同大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。筑波大学非常勤講師、埼玉大学非常勤講師などを経て、現職。分析哲学専攻。20世紀哲学に大きな影響を与えたルドルフ・カルナップの哲学を、形式認識論とメタ形而上学の観点から研究し、その現代的意義を考察している。主な著作に、「分析哲学とモダニズム」(『フィルカル』Vol. 1, No. 1)、『初期カルナップの実在論と反実在論』(東京大学大学院博士論文)など。
この記事を書いた人

- 東京大学大学院学際情報学府修士課程。学部では1年次から哲学の原書テクストを精読するゼミに参加し鍛えられ、ベルクソン哲学で卒論を執筆。現在は人文社会科学がどこから来てどこへ向かうのかについて関心があり、特にそれと社会との交差点であるメディアに照準を定めて研究を進めている。