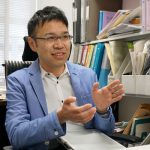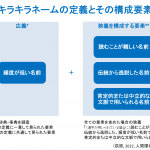日本は「純度100%」を求めがち? ー 東京大学・仁平典宏准教授【後編】
インタビュー前編では、東京大学・仁平典宏准教授がボランティア言説の歴史を研究するにいたった経緯と明治から戦中までのボランティア言説の歴史についてお聞きした。続く後編ではさらに戦後から現在までのボランティア言説の変化をお聞きする。最後には、ボランティアと似た境遇にある寄付行為、さらにはクラウドファンディングという仕組みへの期待についてもお話を伺った。
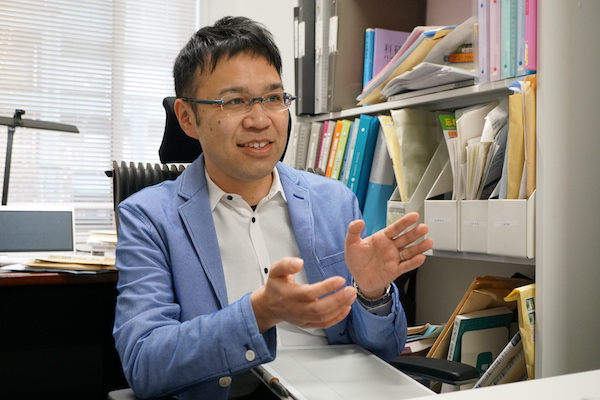
【インタビュー前編はこちら】「冷笑的な私」はどこから?ボランティアの歴史からたどる ー 東京大学・仁平典宏准教授【前編】
戦後、ボランティアはどう語られてきたか
——前編では、明治に誕生した「ボランティア」言説の系譜を第二次世界大戦中までお話いただきました。続けて戦後の歴史についてもお聞きしたいです。
戦後はしばらくのあいだ、戦争という究極のマイナス(反贈与)にいたった戦前への反省が、ボランティア論の中心を占めます。いくら良いことをしているつもりでも、その社会的・政治的帰結に無自覚だと、気がついたら戦争に奉仕していたということになりかねない。そのなかで、国との関係で、ボランティアが踏み外してはならないというふたつの条件が出てきます。ひとつは「国家に対する社会の自律」です。これは民主的な社会で行われる自発的な活動は国家に統制されるのではなく、独立して行う必要があるというものです。もうひとつは「国家による社会権の保障」。憲法で社会保障は国の責任と定められましたが、ボランティアが無自覚に肩代わりすると、その分、社会保障の整備が遅れるというマイナスが生じる。だから、ボランティア活動は、福祉制度の拡充を求める社会運動を伴わないといけないというものです。そうした主張が60年代まで見られます。
60年代は政治の季節ですから、若者たちのなかには学生運動に取り組むひとが多くいました。そのひとたちからすると、政治運動に取り組まないで困っているひとを助けるボランティアのような活動は、社会の矛盾を隠蔽し体制を延命させる自己満足にしか見えませんでした。これに対し、ボランティアを行う若者たちは、目の前に苦しんでいる人達がいるんだから、まずそれを支援しつつ、同時に運動を通じてマクロな構造も変える必要があると主張していました。ボランティア活動と運動や政治は切り離せないと捉えられていたのです。
——戦前の反省もあり、ミクロな実践がマクロなレベルで見たら逆に不利益になっていることに非常に敏感な時代だったということですね。
こうした傾向が大きく変わるのが70年代です。いくつかの背景があります。第一に、高度経済成長が終わり福祉予算が急増していきます。これにより「ボランティアが社会保障の整備を遅らせる」という批判が見られなくなります。第二に、高齢化が進む中で、地域における福祉の担い手を育てようという国の動きが活発化していきます。その旗振り役は文部省と厚生省で、専業主婦や高齢者自身をターゲットとしたボランティア政策がはじまります。
ポイントは参加のハードルを下げることでした。それまでのボランティア論は、宗教や天皇、民主的な社会づくり、政治・運動とのつながりなど、何かしらの大きな物語を参照しながら「贈与のパラドックス」を解決しようとしていました。でもそれらは、一般のひとにとってハードルが高すぎる。これに対して、ボランティア政策のなかで用いられた意義づけは「生きがい」や「自己実現」といったミクロなものです。他者のためとか、社会のためとか、神のためとか、そういった難しいことは考えなくていい、あなた自身の成長のためにやってくださいという形で広めていくわけですね。その政策とともに、それまで一部のひとしか知らなかった「ボランティア」という言葉自体が、徐々に知られるようになっていく。
このようなボランティア育成政策に対しては、「国家に対する社会の自律」を脅かすものとして批判もありましたが、その声は大きくなりませんでした。高度経済成長を経て豊かさが実現したことで、社会的な関心が富の分配の問題から承認の問題へとシフトしていたからです。一言で言えば、物質的には豊かになっているけれども心は満たされていないという問題。当時はこの状況を「疎外」と言いましたが、運動の担い手たちの問題意識も、具体的な政治から、疎外からの人間性の回復といったより抽象的な方向に移っていきました。そうすると、政府が掲げる「生きがい」や「自己実現」という問題系とも近づいていく。
——生きがいや自己実現というある種の「交換」の言葉のもとでボランティア論が収束していくわけですね。
バブル経済に特徴づけられる80年代には、「疎外」という問題意識も抜け落ち、「昔のボランティアは社会のためとか他人のためとか言って偽善臭かったけど、そういうのは自己満足で、自分のために明るく楽しくやる方がいいんだ」という身も蓋もない言説が登場します。さらに90年代に入ると、その「自分のため」という要素を取り入れた「互酬性」という概念がボランティアの定義の中心になります。私が90年代にフィールドワークで経験した、政治から切り離され、「楽しいからやる」という私的な効用を重視するボランティア活動は、このような経緯で生まれたものでした。
2000年代には小泉政権の構造改革により、公共サービスの民営化が進みます。NPO(非営利組織)やボランティアはその受け皿のひとつとして期待されますが、システムの一端を担うためには、自己満足的活動ではだめで、市場でも通用するサービスが必要と言われるようになります。活動の担い手が得る「報酬」も、精神的なものではなく経済的対価が必要で、そのためにNPOは経営体であるべきと言われました。60年代には政治への接近を求められていた社会活動は、市場への接近で評価されるようになります。社会的企業はその文脈で生み出されたカテゴリーです。
以上が贈与のパラドックスというものを中心に見たときのボランティア言説の変化です。「望ましい」とされるボランティアのあり方は次々と変わってきましたが、その変化は「逆効果なんじゃないの」という冷笑的なまなざしに対応する試みのなかで生じていました。そのまなざしは大学生時代の私がもっていたもので、当事者でもあったわけです。この本が出版されたのが2011年の2月28日で、その10日後には東日本大震災が起こりました。その後、市民社会において生じた反原発運動などさまざまな動きは捉えられていないので、その意味で3・11以前の本ではあるかなと思います。
——明治時代には純粋贈与の方向に解決策を求めたのが、そのあとは基本的に「交換」、つまり実はwin-winの関係なんですよということを主張することでボランティアの言説が駆動していったのですね。ボランティアを扱う学問はほかにもありますが、社会学としてボランティアを扱ううえでの特徴は何になるでしょうか。
人文社会系の学問には単純化するとおそらくふたつのタイプの学というものがあります。ひとつは「規範の学」で、つまり何が望ましいのかの価値を探っていく学問です。教育学や社会福祉学は望ましい教育・福祉の状態とは何かという問いの立て方をしますよね。もうひとつは、「事実の学」です。社会科学がこれに含まれますが、何が正しいかという前提を置かない、置くとしてもその探求が主目的ではなくて、対象の構造やメカニズムを探求していく学問になります。
従来、ボランティアは教育学や社会福祉学といった規範の学が対象にしてきました。そこではボランティアの歴史を書くときも、自分が望ましいと思うボランティア像を前提にしたうえで、それを過去に投射するというアプローチを取ります。これに対し私は、何が望ましい/真のボランティアかという前提を置かずに、日本において「ボランティア」という言葉やそれと競合する言葉が、どう運用されてきたのかを明らかにするアプローチを取りました。研究者の恣意的な価値観を対象把握の前提にしないで、言説や表象自体の構成や変化を追尾するというのが社会学における言説研究の特徴になると思います。

やりがい搾取を批判し、偽善批判も批判したい
——これからはどういった研究をされたいですか。
私の今の関心はふたつあります。ひとつは「やりがい搾取」と呼ばれているものの分析です。まず、これまでの日本社会が、どの程度アンペイドワークに依存していたのかを解き明かしたいです。よく指摘されるように、日本の企業は賃金以上に労働者を働かせていて、それが競争力の秘訣と言われたこともありました。また、家庭で主婦が担う育児や介護のアンペイドワークは、公的支出の抑制に寄与してきました。地域でも、それこそボランティアを含めたさまざまなアンペイドワークが活用されています。それぞれを称揚する言説がこの構造を支え、日本の「含み資産」を作ってきましたが、現在の「やりがい搾取」批判の隆盛は、このような仕組みが破綻しつつあることの現れだと思います。賃労働の分析は経済学などで徹底的に行われていますが、私はアンペイドワークの生成・搾取のメカニズムを体系的に明らかにしていきたいと思っています。
——それでは、もうひとつは何になるでしょうか。
もうひとつの関心は、ある意味で今述べたものの対極にあります。やりがい搾取批判は、ボランティア的なものを全部警戒するという議論にもなりがちですが、それはかつての私のような冷笑的なまなざしと紙一重です。でもボランティア的なものを全否定してもいいのでしょうか。欧米では再分配の税制のみならず、高階層のひとによる寄付が、経済的に苦しい人々を支える回路になっています。ノブレス・オブリージュ(高貴な者の義務)の慣習が、今も社会に実装されていると言えるかもしれません。大きな災害が起こったときにはセレブリティが大規模な寄付をしますしね。しかし、日本では芸能人やスポーツ選手が寄付をすると、偽善だ、売名だと言われて、逆にそういうことをやらないひとの方が自分に正直なひととして肯定されかねない勢いです。寄付やボランティア活動を行うということが、すごいリスクになっていますよね。この種のシニカルな偽善批判をどう解体していくかということも同時に考えていきたいです。
このように、やりがい搾取批判と「偽善批判」批判は、方向として逆を向いています。片方では、ボランティア依存型社会を批判しながら、一方でボランティア批判社会も批判するという……。
——寄付もボランティアに似たジレンマを抱えているように思います。私たちが運営しているクラウドファンディングサイト「academist」も寄付の要素が強くあるのですが、最後にクラウドファンディングという仕組みについて先生がどう考えているかお聞かせください。
クラウドファンディングをはじめとするインターネットを介した支援には、とても興味を持っています。日本ではボランティア活動や寄付をしようという人が、外部の批判者から、「お前は本当にその問題を真剣に考えているのか」という純度100%の熱意と、「お前はその問題を本当に理解して、相手の迷惑にならないと言えるのか」という純度100%の知識を求められ、躊躇してしまうことがよくあります。活動しない批判者に限って、ボランティアに対するハードルをやたら高くするのです。これは日本の「市民」という概念が「意識の高い一部のひと」として構築されてきたことともつながっています。
しかし、人間はもっと矛盾に満ちたもので、純度100%を求めること自体無理があります。たとえば、日本に難民が来たら困るから受け入れたくないと思うひとがいるとしましょう。でもそのひとも純度100%の「排外主義者」ではなく、戦火のなかで逃げ惑う親子の報道に胸を打たれ、何とかしたいという気持ちが生じることがあるかもしれません。それは、人間は難民支援にイエスかノーかの択一的な態度を取れる主体としてあるのではなく、矛盾したベクトルの混成体としてあるということではないでしょうか。
クラウドファンディングは、さまざまなベクトルの集積としての個人により適した支援の形だと思います。つまり、ある問題を完全には理解していなくても、「なんかこの問題、気の毒だな」と思う自分は少なからずいて、その断片化された自分ができる範囲で寄付するという形を取れるのがクラウドファンディングだと思います。自分の断片の割合に応じて自分の可処分所得のなかの数%分を寄付すればいいので、純度100%の市民主体を前提にしなくてもプロジェクトを成立させることができるのではないでしょうか。
小説家の平野啓一郎さんも、そうした矛盾に満ちた多元的な存在として人間を捉えようとする「分人主義」を主張されていますよね。個人(individual)ならぬ「分人」(dividual)が何かするうえで、クラウドファンディングのようなオンライン上で気軽に寄付できる仕組みは適合的だと思います。それはまた、純度100%を求めがちな日本の硬直した市民社会の言説空間を、良い意味でほぐしていくきっかけになるのではないかと期待しています。
【インタビュー前編はこちら】「冷笑的な私」はどこから?ボランティアの歴史からたどる ー 東京大学・仁平典宏准教授【前編】
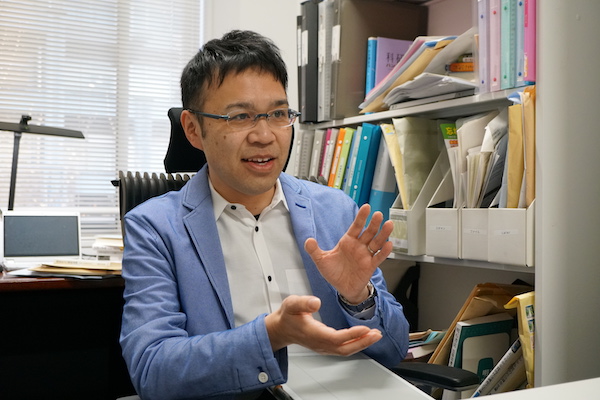
研究者プロフィール:仁平典宏
1975年、茨城県生まれ。東京大学大学院教育学研究科比較教育社会学コース准教授。東京大学教育学部比較教育社会学コース卒業。同大学院教育学研究科博士課程修了。法政大学社会学部准教授などを経て現職。専門は社会学。『「ボランティア」の誕生と終焉――〈贈与のパラドックス〉の知識社会学』(名古屋大学出版会)にて、損保ジャパン記念財団賞、日本社会学会奨励賞を受賞。共編著に『共生社会の再構築Ⅱ――デモクラシーと境界線の再定位』(法律文化社)、『労働再審〈5〉ケア・協働・アンペイドワーク――揺らぐ労働の輪郭』(大月書店)、『若者と貧困』(明石書店)など。
この記事を書いた人

- 東京大学大学院学際情報学府修士課程。学部では1年次から哲学の原書テクストを精読するゼミに参加し鍛えられ、ベルクソン哲学で卒論を執筆。現在は人文社会科学がどこから来てどこへ向かうのかについて関心があり、特にそれと社会との交差点であるメディアに照準を定めて研究を進めている。