新潟から「日本酒学」でうねりを生み出す! – 新潟大学日本酒学センターの挑戦
新潟大学で今年から開講した講座「日本酒学(sakeology)」をご存知だろうか。日本酒の文化、日本酒と健康、日本酒と農業……、というように、日本酒の裏に隠れているさまざまな事象を体系的に学び、日本酒を深く知ることを目指した学問だ。この取り組みを推進する「新潟大学日本酒学センター」には、新潟大学のさまざまな分野の研究者たちが所属しており、日本酒を切り口とした新たな研究アイデアを模索しているという。日本酒学はどのようなきっかけで始まり、これからどのような展開を見据えているのだろうか。今回、新潟大学・高橋均副学長と鈴木一史教授、岸保行准教授に詳しくお話を伺った。
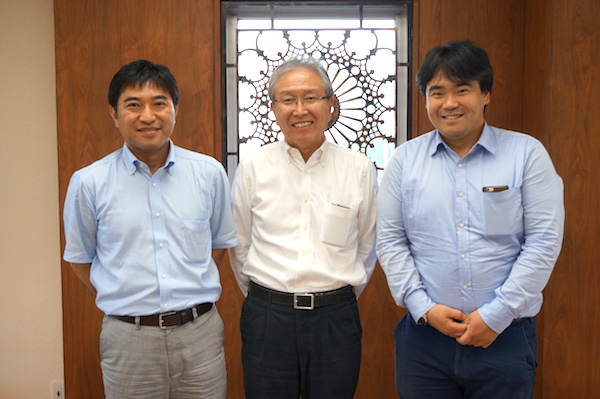
——まずはじめに、「日本酒学(sakeology)」が誕生した経緯について教えてください。
高橋:新潟大学の農学部では、醸造に関連した研究が進められてきました。その点で、日本酒に関する研究をしやすい環境ではあるのですが、それだけが理由で立ち上げたわけではありません。実は新潟県には、全国唯一の日本酒専門の醸造試験場がありまして、そこで美味しい日本酒を造るための研究がされてきたんです。

——県をあげて日本酒の研究を進めていると。
高橋:さらに、市民レベルで日本酒人気が高まっていることも理由のひとつです。「にいがた酒の陣」をご存知でしょうか。これはドイツのミュンヘンで開催されるビールの祭典「オクトーバーフェスト」の日本酒版のようなもので、今年は国内外から約14万人が来場し、新潟県内にある約90の酒造の地酒500種類以上を楽しんでいただきました。この盛り上がりを目の当たりにすると、新潟大学としても何かしなくてはと思います。
——そこで大学として「日本酒学」を立ち上げられた点が大変興味深いです。実際には、どのような研究活動をされているのでしょうか。
高橋:いきなり新しい発見をしようというよりは、まずはスタートラインとして、日本酒をキーワードに私たちがどれほどの話ができるのかを確かめていきたいんです。そこでこの春から、学生向けに「日本酒学」の講義をスタートしました。日本酒の製造や歴史、日本酒と食、日本酒と税金など、日本酒についてのさまざまな視点を提供していきます。
——かなり活況を浴びているという話を伺いました。
高橋:定員が200名のところ、600名くらい集まったんですよ。約2ヶ月のターム制で進んでいて、ちょうど最初のタームが終わりました。まずは学生に日本酒について網羅的に知ってもらうこと、そして新潟といえば酒、酒といえば新潟というメッセージを伝えていくことが出発点です。

——日本酒学を発展させるための土壌を作っているということですね。学生さんだけではなく、どれだけの研究者を巻き込んでいけるかも重要になりそうです。
高橋:研究者の方々に呼びかけたところ、農学系だけではなく人文・社会科学系を含めた10学部から、30人ほどの研究者が集いました。研究者が一同に会すると「私は日本酒学でこういうことができそう」というような話が自然にはじまるわけです。将来的には、学部に負けず劣らずのセンターができるのではないかと期待しています。
——楽しみですね。学外との連携も考えられたりしていますか。
高橋:先月まさに、鈴木先生と岸先生が「ワイン学」で有名なボルドー大学を訪問してきました。ワイン学は英語で「Enology(エノロジー)」と呼ばれており、大学院ではテイスティングや、ぶどうの選定・栽培などのプログラムを受講することができます。日本酒学の構想を話したところ、いろいろとアドバイスをいただけただけではなく、すぐにでも協定を結びたいという提案もいただきました。2018年12月までには基本合意書を締結するということで、現在話が進んでいます。人材交流を活性化させていくことで、さまざまな学部で基礎的な素養を培った学生さんが、修士課程では日本酒を学びたいと思える環境を作っていきたいです。
——日本酒のことを網羅的に学んだ後には、実際に研究活動を進めることになると思うのですが、現段階で考えられる研究アイデアはありますか。

岸:私の専門は、経営学と社会学が交差する領域で、研究のひとつの柱として「文化製品の海外展開」というものがあります。ある地域に根ざした文化が、その地域をどのように超えていくのか、もっというと、国境をどのように超えて、超えた先の人たちにどう消費されるかということに関心があります。
新潟県の酒造さんを訪問すると、みなさん醸造に対する熱い想いがやはりあるんですよね。その想いがどのようにお客さんの手に届き、どう消費されるのかを理解することで、日本酒学の発展に貢献していきたいです。
——現在は、日本酒は海外でどのように消費されているのでしょうか。
岸:海外に日本料理店が増えているので、日本酒の消費量も増えています、ただ、まだまだ普及しているとは言えません。なぜかというと、海外では日本酒を日本料理店で飲んでいるからです。つまり日本酒を飲むことが、文化体験の一環としてみなされているんですね。でも私たち日本人は、フランス料理店に限らずあらゆる場所でワインを飲んでいます。文化体験を超えてどのように日本酒を飲むようになるのかということは、私のいまの研究テーマのひとつです。
——ワインが普及した経緯から学べることが多そうです。
岸:そうですね。ひとつのヒントは、ワインの世界で言われている「マリアージュ」です。ワインを飲むときには、ソムリエが食事との相性を含めて提案してくれますよね。一方で日本酒の場合、そういうことはなかなかありません。
——ワインに比べると、料理との相性を語られることは少ないかもしれませんね。
岸:でも、少しずつその流れは出てきています。海外に輸出する酒蔵さんを見てみると、ワインボトルに日本酒を入れたり、食べ合わせを意識したラベルを作っていたりするんですね。ただそれだけで普及させられるわけではありません。日本酒はアルコール製品ですので、たとえば「健康」との関係性がキーワードに売り出していくということも必要になります。
——そうなってくると、他分野の研究者との連携が必要になりそうです。

鈴木:この辺りに関しては、日本酒学の講義「脳とアルコール」で取り扱ったテーマでもあるのですが、実際には食品科学や脳科学の専門家の方々と研究を進めていくことになります。
また、先ほど岸先生の話にもありましたが、日本酒とそれに合う食事の「マリアージュ」も研究テーマとしておもしろいと思います。食べ合わせの良し悪しは経験的に決められています。食品科学の研究者がマリアージュの科学的根拠を追求するというのは、日本酒学のひとつの研究テーマとして重要です。
——日本酒が作られてからお客さんの手に届くまでに、さまざまな研究テーマが出てきそうです。鈴木先生ご自身としては、どのような立ち位置で研究を進めていかれるのでしょうか。
鈴木:まずは、醸造試験場との共同研究のなかから、日本酒の研究を進めていきたいです。私の専門は応用微生物学なのですが、日本酒学センターのメンバーに農学部以外にも微生物を扱う研究者がいて、なかには今は植物をやっているが、昔は酵母を研究されていた方もいらっしゃるんですよね。このような異分野の研究者や、県の研究者と一緒に議論を進め、これまで出てこなかった隠れたアイデアを出して、新しい分野を開拓していきたいです。
——日本酒学を立ち上げる過程で、さまざまな分野の研究者や学生、県の研究者、蔵元の方々、日本酒に興味を持つ市民など、多様な人たちが関わっています。今回の取り組みは、異分野融合型の研究を進めること以上に、大学のありかたを問い直す試みと捉えられるのではないでしょうか。
高橋:これだけの人たちが日本酒学の取り組みに参加していることを目の当たりにすると、大学は街のなかにあって街のなかで生きているのだなとつくづく感じます。こういうものが大学のスタートラインになくてはならないんだと市民や県民の方々から評価されているわけですからね。
——日本酒学の試みを継続的に広げるポイントはどこにあるのでしょうか。
高橋:人文・社会科学系の分野だと思います。それにも関わらず、地方大学の人文系の学部は潰しても良いというような意見が蔓延しているのは、大変残念なことです。日本酒学センターの取り組みによって、人文・社会科学系が社会をリードして、実際に社会を変えていける力があるということを示していきたいです。大学としても、大きな指標を持つことができましたよ。
——新潟大学発で、世界に日本酒学の取り組みが広がっていくと良いですね。
高橋:いずれは日本酒学が学会のような組織になり、新潟県以外の研究者ともつながり、継続的に発展していける組織ができるといいなと思います。幸いなことに、日本酒は市民のみなさんにも受け入れられやすいテーマですから。市民参加を促す形で「日本酒学」というひとつのうねりを生み出していきますよ。
この記事を書いた人

- アカデミスト株式会社代表取締役。2013年3月に首都大学東京博士後期課程を単位取得退学。研究アイデアや魅力を共有することで、資金や人材、情報を集め、研究が発展する世界観を実現するために、2014年4月に日本初の学術系クラウドファンディングサイト「academist」をリリースした。大学院時代は、原子核理論研究室に在籍して、極低温原子気体を用いた量子多体問題の研究に取り組んだ。







