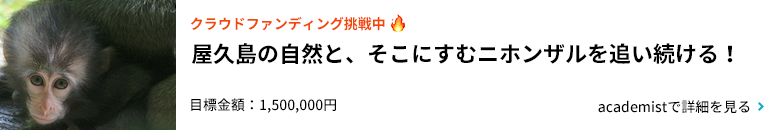なぜ、命がけでフィールドワークをするのか? – ゴリラ研究の第一人者 京都大学・山極寿一総長に聞く
屋久島でニホンザルの生態調査を行っているグループ「ヤクザル調査隊」が、academistのクラウドファンディングで調査費用を募っている。
ヤクザル調査隊は、1989年に数十人の研究者によって結成された。それから30年間、多数のボランティア調査員の協力を得ながら、屋久島にすむニホンザルの生態や自然環境の移り変わりを調査することで、ニホンザルの社会が長期にわたってどのように変動しているのか、世界的にも貴重なデータが蓄積されつつあるという。
ヤクザル調査隊の調査では、電気・ガス・水道のない屋久島の山の上で、数十人が1週間以上キャンプをしながら生活し、そこに生息しているサルの追跡を行う。今回は、こうしたフィールドワークを実施する意義について、ゴリラ研究の第一人者であり、かつてヤクザル調査隊の一員でもあった京都大学 山極寿一総長に聞いた。
【関連記事】大学というジャングルでフィールドワークをするために、学生は大学へやってくる – 京都大学・山極寿一総長の「大学観」

「人間を知る」ために霊長類を研究する
——山極先生が総長を務められている京都大学には、霊長類研究所という日本で唯一の霊長類学の総合研究拠点があります。先生ご自身も、霊長類に属するゴリラについて長年研究されてきたと思いますが、まずは「霊長類学」とはどのような学問なのか、お聞かせください。
京都大学霊長類研究所には現在10の研究分野があり、霊長類に対してさまざまなアプローチで研究が行われていますが、僕がやってきたことを中心にして語るとすれば、霊長類学には「人間を知りたい」という動機があります。人間は昔から人間であったわけではなく、「人間のようなもの」から進化して人間になったといえます。ではその「人間のようなもの」とは何だったのかということを霊長類学では調べます。
たとえば今我々は言葉を喋っていますが、ちょっと前まで人類は言葉を喋っていなかったわけですよね。では言葉を喋っていないときの人類のコミュニケーションって、一体どのようなものだったのでしょうか。あるいは今、我々人間は調理したものを食べて生きていますが、調理をしはじめたのも人類の長い歴史のなかでは最近の話ですよね。調理していない食べものを食べているとき、人類はどういう暮らしをして、どういうものを食べていたのでしょうか。
人間の身体というのは、文明に応じてそう簡単に変化するものではありません。そもそも人類が食料を生産しはじめたのは約1万2000年前といわれていますから、それまでは自然の恵みにのみ頼って生きていたわけです。身体的には、人間はまだその世界にいるといっても良いでしょう。もしかすると、身体だけでなく心もそっちの世界にいるのかもしれない。
とするならば、人間の過去を調べるためには、今の人間からイメージするよりも、人間とは違う暮らしをして人間に似た身体をもっている動物の研究をする必要があります。それによって、なぜ人間のような身体や心が生まれたのか、ということに迫れるわけです。
——人間に似ている霊長類の動物を調べることで、人間について理解していこうということですね。
たとえばニホンザルは、今から45万年から60万年ぐらい前に日本列島に渡ってきました。一方で、人類が日本列島に渡ってきたのはたった3万年前。人間は、日本列島の居住者としては新米なんです。その証拠に、ニホンザルには冬毛と夏毛があります。夏になると毛を短くしてスカスカの毛で涼しく過ごし、冬には脂肪に富んだフカフカの毛を長く伸ばして、まるで毛布に包まれているかのようなあったかい格好をしています。しかし、熱帯が起源の人間は、夏毛も冬毛も持っていない。人間とサルとでは、日本列島への適応の仕方が違うということです。

ではなぜ、人間が日本列島で生き延びられたかというと、文明や道具をつくって自然環境とのあいだにインターフェースを設けることで、さまざまな環境の変化に耐えてきたからですよね。逆に、文化や文明をまったく持っていないニホンザルはどのようにして、北から南までさまざまな変化に富む日本列島の自然環境のなかで生き延び、なおかつ身体に変化をもたらしてきたのでしょうか。人間に近縁で類人猿に分類されるオラウータンやチンパンジー、ゴリラは、日本列島には来なかったわけですから。
一般的には類人猿の方が知能が優れているというけれど、彼らは熱帯雨林から一歩も出なかった。でもサルは熱帯雨林の外へ出たわけです。ヒヒも、ニホンザルの仲間のマカクも、熱帯雨林から出て、遠く雪の降るような地域まで足を伸ばして、そこで立派に生き延びている。では人間に非常に近い類人猿と、人間からちょっと遠いサルのあいだに、一体どういう違いがあったのでしょうか。その違いが、類人猿が住めない地域にサルが足を伸ばすことができた理由になっています。
このように、人間に近い、あるいは人間から少し遠い動物の生態や社会を調べることで、なぜ類人猿の仲間のなかで人間だけが熱帯雨林を離れてサルよりもさらに寒い地方へ足を伸ばすことができたのか、などといった人類の進化におけるさまざまな問いに迫ることができるのです。

命がけでフィールドワークをする理由
——山極先生は長年、ゴリラについて研究するためにフィールドワークを行われてきましたね。フィールドワークはどのように進めていくのでしょうか。
まずゴリラを慣らすのに通常5年ぐらい掛かります。最初は人間を見ると「グワッ」と吠えて、逃げていくだけ。ゴリラの声しか聞こえない状態が何か月も続きます。そこから1頭でも特徴のある個体を見つけて特定のグループを追い続けられるようになると、毎日毎日それを追っていくことになります。
——どうやって特定のゴリラを追い続けていくのですか?
新しい足跡、新しい糞、そして新しいベッドサイトを手掛かりに追っていきます。ゴリラは毎日毎日、木の上ややぶの中など違う場所にベッドをつくって寝ています。そのフレッシュなベッドサイトに行き当たれば、後は足跡を追っていけば出会えます。したがって「今朝のベッドサイトを見つけること」がゴリラ研究のフィールドワークの至上命題です。
ただ、ゴリラに出会っても違うグループのゴリラであることも多いです。ゴリラは縄張りがないうえに、1年間に20〜40km2ぐらいの広い範囲を動くので大変なんですよ。だからもう、朝早く起きて、ベッドを見つけて、追うしかない。目的のグループでなければ、また別のベッドサイトを見つける。人間側はひとつのグループじゃ足りないから、3つ4つのグループで手分けしてゴリラを探して、トランシーバーで連絡を取り合う。ゴリラを発見したという連絡があれば地図やGPSを頼りにそこまで移動していく、という流れで動くわけです。
——とても大変そうです……。
大変ですよ。でも慣れちゃうと、もうびっくりするぐらい簡単(笑)。たとえば「ここにゴリラが来たのであれば、きっと明日はあのフルーツを食べるためにあの場所へ行くよね」といったような予想がつくようになるので、そこで待っていれば良いんです。そうしていくうちにゴリラはだんだんと人間に対して吠えなくなってきますが、まだ緊張が解けないためなかなか近づかせてはくれません。さらに今度は攻撃してくるようになるんです。僕たちは執拗にゴリラを追っているストーカーみたいなもんですから(笑)、うるさいと思われてしまって、胸を叩いて追い払われたり、あるいは直接攻撃されたり……。僕も頭や足を噛まれて、大怪我したことがあります。それを乗り越えるとようやく、ゴリラの近くにいても「まぁ、いっか」と思ってもらえるようになるんです。こうして5年くらい掛けてやっとゴリラ全員に名前をつけることができるまでになるわけです。ここまでいかないと、ゴリラの社会の研究はできません。
——ゴリラに名前を付けるとのことですが、ゴリラ一頭一頭の違いってわかるものなんでしょうか。
簡単にわかります。ゴリラがみんな一緒に見えてしまうのは、彼らの特徴を見ることに慣れていないから。ゴリラの特徴を見ることにだんだん慣れてくると、それぞれ違うということが一瞬にしてわかるようになります。ニホンザルでもそうなんですよ。ニホンザルの研究をしていた大学4年生のときには、100頭以上のニホンザルの顔を覚えましたよ。覚えはじめて2週間ぐらいはぜんぜんわからないんだけど、あるとき突然わかるようになる。それは、名前の付いたニホンザルが夢に出てくるようになったとき(笑)。そうすると、「あっ、頭の中に入ったな」って感触が出てくるんです。
——夢にまで出てくるなんて、おもしろいですね。ゴリラを追うときには共同研究者のみなさんとグループを組むのですか?
共同研究者もいますが、森のなかで迷わないようにするためにトラッカーという森のことをよく知っている人も同行します。迷っちゃったら帰ってこれなくなりますから。トラッカーを連れずにフィールドワークへ行ったときには迷いましたね。一晩二晩森で寝たことは何度もあります。
——おひとりで迷われたこともあるんですか?
ひとりで迷って、バッファローに追いかけられて木の上で半日過ごしたこともありますよ。ゾウに追いかけられるのが一番怖い。ゾウにやられたらまず助かりませんから。トラッカーを連れて行ってもトラッカー自身が迷うこともあるので、トラッカーと一緒に野宿したことが何度もありますよ(笑)。そういう過程を経てやっと、ゴリラはこっちに心を開いてくれるようになります。
——命がけでフィールドワークをされていたんですね……。
なんでそこまで苦労してゴリラの群れの中に入んなくちゃいけないかというと、彼らは言葉を持っていないから。たとえば、ゴリラにデータロガーを付けてGPSで追って、どこで誰が何をしているのかという情報を得ることは、可能といえば可能ですよね。あるいはビデオを撮影して個体同士がどういうことをしてるのか詳細に分析することもできます。でも僕はそれをやりたくない。なぜかというと、「微妙な感覚」っていうのがあるわけですよ。彼らの行動や社会を本当に理解するためには、自分の身体で体験する必要があると思うんです。
——「微妙な感覚」とは、どういうものでしょうか?
子ども、あるいは雌/雄がそばにいるっていうだけで、彼らの行動は変わります。人間もそうだと思いませんか? その微妙な社会的な雰囲気をその現場で体験することによって初めて、彼らの社会がどうできているのかを想像することができるんです。
そこには匂いや肌触り、音も入っています。ビデオの音源のようにある定点から撮っている音ではなく、背景がちょっと違うような彼らが聞いているのと同じ音を聞けるんです。現場感覚は、実は社会の研究には重要なんです。1頭1頭の行動だけを見ているわけでも、2頭のインタラクションを見てるわけでもなく、全体の雰囲気を見なくちゃいけないわけですから。
しかもそれを、当事者として見るということが重要なんです。ゴリラ研究の場合には、常にゴリラの人間に対する感覚を、ペット感覚にするように心がけていました。ゴリラにとっての我々人間は、人間にとってのネコのような存在にならなきゃいけないんです。我々人間に関心を持たれたらダメなんですよ。
ネコってハッと気がつくと、自分のそばに座っていたりしませんか? でも普段、ネコが自分の周囲にいても気に止めないですよね。ゴリラにとってペットのような存在になることで、彼らの日々の暮らしを一切邪魔せずに、冷静な観察者になることができるんです。
——空気のような存在になるということですか。
空気のような存在だけど、空気になっているわけじゃない。ネコだって、実は当事者として現場にいていろんなものを感じているわけですよ。だけどそこに機械を持ち込んでしまったら、それらすべてが削ぎ落とされてしまいます。だからフィールドワークでは時間を掛けて苦労してでも、ゴリラやサルの中に入っていく必要がある。そしてそこで感じたことを、なんとかして表現しなければなりません。

「白目」から相手の気持ちを読み取るのは人間ならではの能力
——これまでの山極先生の研究で「表現」されたものの例を教えていただけますか。
たとえば、僕が発見したのはゴリラの「覗き込み行動」。ゴリラって、相手の顔を覗き込んで、10cmくらいの距離で顔と顔を合わせるんですよ。これはゴリラの群れの中にいたときに、ゴリラが実際に僕に対してとった行動です。
それまで僕はニホンザルの研究をしていましたが、ニホンザルにとっては、相手を見つめること=威嚇です。ニホンザルは、顔を見つめると威嚇されていると感じ、逃げたり攻撃してきたりするわけです。動物園などに行くと、サルの檻の前に「サルの顔を見つめないでください」と書いてありますよね。それが彼らの社会のルールです。
だから僕は初め、ゴリラの場合でもそうだと思って、ゴリラの顔をなるべく見つめないようにしていたわけです。ゴリラが僕のほうを見たら視線を外していました。でもゴリラがこっちまでやってきて見つめ出すもんだから、これはヤバいなと思って避けた。そうすると、回り込んでまで顔を近づけてきて……そのときは「あれ、何してんだ!?」と思って、じっと下を向いていることにしたんです。すると、「ウー」と唸って、そして後ずさりして、不満そうに立ち去って行った。
そのときに「これは、ニホンザルとは違うな」と感じました。そこでゴリラの行動をもう一度注意深く見てみると、ゴリラ同士が毎日のように顔と顔を見合わせるという行動をしているわけです。「あらっ!」と思いましたね。事例を記録していくと、挨拶だったり、仲直りだったり、交尾の誘いだったり、遊びの誘いだったり、仲裁だったり……と、顔と顔とを見合わせる行為がいろんなところで出てきたんです。それで、これは彼らにとって非常に重要なコミュニケーションだということがわかりました。これは論文にもまとめています。
——ゴリラにとっては顔と顔とを見合わせることがコミュニケーションになっているんですね。
そこから「じゃあ人間にとってこの行動はどういう価値を持っているんだろう」と問い返してみた。人間はそうした行動をとりませんよね。誰かと話をするときにも一定の距離を保っています。そもそも話をするのに、近くにいて顔と顔とを向かい合わせる必要すらないじゃないですか。だって、音声で意味を伝え合えるんだから。言葉を交わし合うために対面しているわけじゃない。
でも人間は対面したがる。これは、ニホンザルとは違ってゴリラとは同じなわけです。だけど対面するときに距離を置くのは、ゴリラとは違う点。なんでこうした違いがあるんだろうと思ってみたら、「目」に違いがあったんです。
——「目」ですか?
そうです。ゴリラの目って真っ黒なんです。ゴリラは言葉を持っていないうえに、目が真っ黒。だから近づいて顔を合わせる必要があるんじゃないだろうか。でも人間の目って白目がありますよね? 目がキョロキョロしたりパチパチしたりすることによって、相手の気持ちがわかる。集中しているのか、どこかに注意を逸らしてるのか、別のことを考えているのか、白目があることによって少し離れた場所からだと相手の状況がわかるわけです。そしてそれが、言葉を伝える支えになっているんです。
我々人間が言葉を交わし合うときには、相手の顔を見て、目の動きを見て、相手の気持ちをモニターすることが非常に重要です。現代人は虹彩の色こそ違えど、どの民族もみんな白目を持っている。白目を通じて相手の気持ちを推し量る能力は、人間誰もが持っているものです。
——確かに「目は口ほどに物を言う」ともいいますしね。
言葉はそれぞれの民族で違うのに目の特徴が同じであるということは、人類が地球上に広がっていろんな言語を編み出す前、我々の祖先はすでにこの白目を持っていたということです。でも人間に一番近いチンパンジーも白目を持っていません。つまり人間だけにこの目が発達したということになります。だからなんらかの大きな理由があったわけです。
ちらっと見るだけじゃなくて、じっくり目を見て対面することによって、より相手のことが深くわかります。だから人間は、電話で済む話でも大事なときには面接をします。それは、単にそのときの相手の気持ちを確かめるだけではなく、相手の人格だとか、相手の人間性みたいなものを見たいからなんですよね。しかも重要なことは、人間は生まれつきそういう能力を持っているということ。非常に大切な能力で、本能に近い能力ということなんです。これが、ゴリラと人間との違い。実際にゴリラの社会に入って体感しないとわからないことです。
(取材:柴藤亮介 撮影:大塚美穂 文・構成:周藤瞳美)

京都大学 山極寿一総長 プロフィール
1952年東京生まれ。京都大学理学部卒、同大学院理学研究科修士課程修了、同大学院理学研究科博士後期課程研究指導認定、退学。京都大学理学博士。(財)日本モンキーセンター・リサーチフェロー、京都大学霊長類研究所助手、同大学院理学研究科助教授、教授を経て、現在京都大学総長。『家族進化論』『ゴリラ』(東京大学出版会)、『暴力はどこからきたか』(NHKブックス)、『「サル化」する人間社会』(集英社)など、ゴリラや人類の進化に関する著書多数。
【関連記事】大学というジャングルでフィールドワークをするために、学生は大学へやってくる – 京都大学・山極寿一総長の「大学観」
この記事を書いた人
- academist journal編集部です。クラウドファンディングに関することやイベント情報などをお届けします。