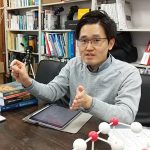【「政策のための科学」とは何か? #2】国際比較研究から運営費交付金の論点を考える – 政策研究大学院大学・林隆之教授
2004年の国立大学法人化以降、国立大学に渡る運営費交付金が年間約1%ずつ減少してきた。大学関係者は教育と研究の基盤が揺らぐため運営費交付金は減らすべきではないと主張する一方で、財務省等は国立大学は税金だけに頼らずに自ら稼ぐべきであると反論する。このような議論は長く続いており、両者の溝が埋まる様子はみられない。国立大学を継続的に発展させたいという考えは共通しているのにも関わらず、なぜこのような擦れ違いが生じるのだろうか。
政策研究大学院大学・科学技術イノベーション政策研究センター(SciREXセンター)では、大学の教育研究政策の研究を行うなかで、国内外の運営費交付金の配分に関する調査研究を進めている。連載第2回となる今回は、科学技術政策を専門とする同大学・林隆之教授に国内外の運営費交付金の動向と今後注目すべき論点について詳しくお話を伺った。

リーマンショックを機に世界各国の交付金事情が変化
——国内の運営費交付金は、年間約1%(約100億円)ずつ削減されていますが、その妥当性や今後の戦略を考えるうえでは、諸外国の状況を知ることが重要ではないかと思います。まずはじめに、諸外国の運営費交付金の状況について教えていただけますでしょうか。
2008年のリーマンショック以降、主にヨーロッパやアメリカでは国や州から大学に渡る交付金が大幅に減りました。ヨーロッパをみれば、国によって状況は異なるのですが、2012年が2008年よりも交付金を減らした国が最も多い年であり、その後に少しずつ戻しています。
——リーマンショックをきっかけに減少していたのですね。そうしたなかで、逆に交付金が増えた国はありますか。
たとえばドイツでは、2008年以降に交付金が20%以上も増えています。というのもドイツでは、連邦が大学生の数を大幅に増やすための教育政策を進めていたのですが、学生数が増えることによる経費負担に大学が耐えられなくなりました。これを機に、州の責任のもとで運営されていた大学が、州と連邦により運営されることになり、結果的に連邦からの公的資金の増加につながったということです。
——交付金が大幅に削減された事例があれば教えてください。
イギリスでは交付金の20%以上が削減されました。その理由は、イギリスが大学の教育部分に交付金を渡すことを止め、大学の授業料を年間3,000ポンドから9,000ポンドに引き上げたからです。学生の授業料負担が増えれば、当然ながら資金ニーズは高まります。そこで国は、学生にお金を貸し出し、就職後に返済する学生ローンの仕組みを導入しました。国が大学に直接交付金を渡すのではなく、学生から人気のある大学に授業料という形で間接的にお金が入るようにしたんです。
——なるほど。学生マーケットに委ねる形で、交付金を「競争的」にしたということですね。
そして国は、大学間の健全な競争を促すために、大学選択に必要な情報を入学希望者に届ける役割を担うことにしました。公的な立場から各大学を評価し、どこの大学がどう優れているのかという情報を学生に与えるようにしたのです。これは、学生が主体的に大学をつくるというイギリスならではの文化があったからこそ、実現したように思います。日本では考えにくいことですが、イギリスでは大学の経営会議に学生の代表も参加していますからね。
——文化によって取るべき政策も変わるということですね。アメリカはどうですか。
アメリカもヨーロッパと状況はそこまで変わらず、リーマンショック以降に減額したぶんを徐々に戻してきているところです。ただ、交付金の額はリーマンショック以前の時点には及びません。これからの大学経営は、連邦や州からの交付金や授業料頼みでは、どこの国も難しくなるでしょう。大学経営における資金源の多様化は、世界各国の共通課題であるように思います。

日本の運営費交付金の論点は、「総量」ではなく「配分方法」
——アメリカやヨーロッパと同じように、日本にもリーマンショックの影響はあったのでしょうか。
日本の場合、共同研究費などの民間資金は影響を受けたと思いますが、交付金に関してはリーマンショックの影響は大きくありませんでした。2004年の国立大学法人化以降、国立大学への運営費交付金が毎年1%削減する方針が採られてきたのですが、競争的資金とあわせれば国立大学に配分される公的資金は全体として増えてきています。
——世界各国ではリーマンショック前の水準に戻っていない一方で、日本では国立大学への公的資金は全体として増えてきていると。
そうですね。国内では、運営費交付金の削減を問題視する声があげられていますが、日本だけが削減されているわけではありません。公的資金全体の額が増えていることを考えると、運営費交付金の総量削減を訴える声は国には届きにくいように思います。
——運営費交付金の総量は論点になりにくいということですね。では、日本の課題をどのようなところに見られていますか。
私は、運営費交付金の総量ではなく配分方法について議論すべきではないかと考えています。国立大学法人化以前は、学生や教員の数に単価をかける形で交付金の額の多くが決まっていました。しかし法人化後は、法人化の前年の交付金の金額を基準に、それが年間1%ずつ減る仕組みになったのです。法人化当初は、予算に自由度を残したほうが、大学として戦略的に物事を進めやすくなるという考えがあったのでしょう。
——年間1%削減されてはいるものの、どこの大学も一律に削減されているのであれば、配分方法としては問題ないように思えます。
実は、毎年1%の削減に加えて第3期中期目標期間(2016年度~2021年度)から、運営費交付金の傾斜配分が始まりました。各大学が交付金の一部を持ち出して、その金額が競争的に再配分されるという動きです。2016年度は合計100億円、2017年度は200億円、2018年度は300億円というように、毎年100億円ずつ持ち出し分が増え、再配分額は年々増大しています。
——どのような基準で再配分されるのでしょうか。
各大学がそれぞれの大学改革案を文部科学省に提出し、KPIの達成状況に応じて配分額が決まります。しかしここには、大きく2つの問題があります。まずは、当たり前のことですが、大学は改革案を実施するためにお金がかかるということです。そもそも各大学から交付金を持ち出しているので、持ち出し額より大きい額をもらえたとしても、その差額で改革案を実施し、かつ減らされた予算で通常どおりの教育と研究を行わなければなりません。また、再配分された予算は「機能強化経費」と位置付けられており、教育や研究に自由に使える「基幹経費」と比べると利用用途が限定的であることも、大学運営を難しくしている要因になっています。
——2019年度からは、この再配分額が10%程度(約1,000億円)になるといわれています。
基幹経費が10%も圧縮されるため、ますます人を雇いにくくなるでしょう。また2019年度以降の施策では、再分配の基準も問題だと思います。教育や研究を進めるはずの予算を再分配するはずなのに、再分配先の選定基準が、学内に年棒制を導入したかどうかや、管理会計を取り入れているかどうかなど、教育や研究とは関係のない観点になっているのです。諸外国の動向を調査すると、日本のように前年度額ベースや、教育研究面ではない改革度合で予算を配分している国はほとんどなく、教育と研究の実績に基づいて交付金を配分している国が多いことが明らかになってきました。

実績に基づいた配分で、「競争性」と「安定性」のバランスを
——諸外国の状況について具体的に教えていただけますか。
交付金の配分方法は、いくつかに分類できます。まずは、たとえば高等教育を担当する官庁と大学が非公開で交渉をして金額を決める「ネゴシエーション(Negotiation)」。次に、日本の運営費交付金のように、前年度額など歴史的に決まっている額で配る「ヒストリカリー・デターミンド(Historically determined)」。他には、学生数のようなインプット指標ではなく、学位授与数のようなアウトプット指標で配る「ファンディング・フォーミュラ(Funding formula)」。また、たとえば国が国際化を進めたいときに、私たちの大学では留学生を何人受け入れますなどという形で大学と国で契約を結ぶ「パフォーマンス・コントラクト(Performance contract)」を導入している例も見られます。
このように整理されるなかで、世界的には実績に基づいて交付金を配分する「パフォーマンスベースのファンディング(Performance-based funding)」にシフトしている状況にあります。実際に欧米のフォーラムに参加しても、今後は大学のパフォーマンスを追及するべきだという議論が盛んに行われています。
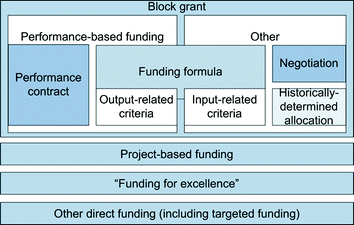
引用元:Pruvot E.B., Claeys-Kulik AL., Estermann T. (2015) Strategies for Efficient Funding of Universities in Europe. ,The European Higher Education Area.
——教育や研究のパフォーマンスに基づいて配るとなると、毎年運営費交付金の額が変動することになりませんか。
運営費交付金の額が毎年変わるのは困るという意見はあるかもしれませんが、他の国ではたとえば学位授与数や論文数が指標になっています。これらの指標は毎年一定ではないものの、大きく変わることもありませんよね。競争的な要素を取り入れながらも、安定的にお金を配分できる仕組みが必要なのだと思います。
——競争性と安定性のバランスを上手く取ることが重要になる、と。そうすると、何を指標にするかを決める必要がありそうです。
そうですね。定量指標と定性指標のバランスをどう取るかは、極めて難しいところです。どの分野も論文数のような定量指標だけで評価できるわけではありません。人文科学系の研究業績を考えても、論文数や書籍数だけで評価してよいかといえばそういうわけでもなく、学術書の翻訳や歴史資料の編纂、美術館などの展示資料の監修など、一般的な定量指標では含まれない業績があります。それらを無視してしまうと、該当分野はどんどん衰退してしまいます。定量指標だけではなく、その分野のことを理解している人による定性指標を決めなくてはなりません。
研究者コミュニティ自らが、研究の意義を社会に示していく
——諸外国の取り組みで、定性指標を考えるヒントとなる取り組みがあれば教えてください。
イギリスでは2014年から、研究成果の評価において、学術的な質だけでなく、社会、経済、文化に与えるインパクトも問われるようになりました。たとえば政治学分野であれば「研究成果がこの政策に活きています」とか、医学分野であれば「研究成果が医療に応用されることで疾病率の低下にこれだけ効果がありました」というように、学術研究の社会に対するインパクトがエビデンスを踏まえて評価されるようになったのです。これはすべての研究者のすべての研究成果がその対象というわけではありません。各学科からの研究成果のうちで10人に1件くらいの数で、社会的なインパクトを説明してくださいという方法です。その結果、研究者たちも学術的な成果を示すだけではなく、社会のなかでの研究成果の価値を考え、それを発信するようになっています。
——それは素晴らしいですね。一方で、社会にインパクトを与えにくい分野もありそうですが。
そうですね。イギリスではその分野の社会に対するインパクトを研究者コミュニティで考え、決めていくことによって社会からの理解を得ようとしています。たとえば、人文・社会科学系は社会に対するインパクトを測りづらいという議論は、日本と同様にイギリスでも出ています。そこでたとえば人文学のリサーチカウンシル(資金配分機関)では、研究者たちが自分たちの分野の研究成果が社会に与えるインパクトとはどのようなものか議論を行い、レポートをだしています。大学の研究者が自分たちの研究分野の学術的価値と社会的価値はどのようなものであるかを伝え、その内容を評価基準に落とし込んで評価を行い、その結果を社会に示していくことで、社会からの理解を得るという仕組みができているということです。
——自分たちで研究の価値を議論し、社会からの理解を得るというのは新鮮な発想ですが、本来そうあるべきかもしれません。日本では常に「上」から指標が降ってくるので……。
イギリスのこういうところは参考にすべきかもしれません。人文・社会科学系は、学術と社会の境界がクリアではないこともあり、他分野よりも社会的な貢献をアピールしやすい面があると思います。一般の方々も研究者の書いた書籍は読みますし、そもそも研究者は社会課題などを研究対象にしているので、きちんと議論をして自分たちで指標を設定していけば、人文・社会科学系不要論のような議論は出てきづらくなるのではないでしょうか。ただ、日本でそうした議論がほとんど進んでいないというのは、悩ましいところです。今後、運営費交付金を最適に配分していくためにも、さまざまな学術コミュニティがそれぞれの価値を明確にしながら、社会とのコミュニケーションを進める営みが必要になると考えています。

政策研究大学院大学・林隆之教授 プロフィール
政策研究大学院大学 政策研究科 教授/独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構 客員教授
専門は、科学技術政策、科学計量学。研究活動および科学技術政策の評価システム・手法・指標に関する研究を対象としており、文部科学省政策評価に関する有識者会議委員や国立大学協会政策研究所運営委員会委員なども務める。SciREXセンターでは、⼤学のマネジメントに関する制度・国際⽐較研究から⽇本の⼤学の特徴や課題を特定する「イノベーションシステムを推進する 公的研究機関の制度的課題の特定と改善」プロジェクトの全体統括を行う。
[PR] 提供:政策研究大学院大学 科学技術イノベーション政策研究センター(SciREXセンター)
この記事を書いた人

- アカデミスト株式会社代表取締役。2013年3月に首都大学東京博士後期課程を単位取得退学。研究アイデアや魅力を共有することで、資金や人材、情報を集め、研究が発展する世界観を実現するために、2014年4月に日本初の学術系クラウドファンディングサイト「academist」をリリースした。大学院時代は、原子核理論研究室に在籍して、極低温原子気体を用いた量子多体問題の研究に取り組んだ。