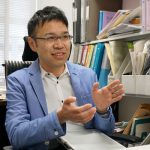茨城大学のこれからを考える!「みんなの”イバダイ学”シンポジウム」イベントレポート
12月22日(土)に茨城大学で開催された「みんなの”イバダイ学”シンポジウム」にアカデミスト代表の柴藤がゲストスピーカーとして参加しました。

みんなの”イバダイ学”シンポジウムは、来年で設立70周年を迎える茨城大学が、学長から大学教員、学生、さらにはビジネスパーソン、地域住民まで多くの方を巻き込み、これからの茨城大学のビジョンについて根本から考えるために主催したイベントです。

イベントの第1部では教育社会学者であるオックスフォード大学 苅谷剛彦教授による基調講演が行われました。
苅谷教授の講演テーマは「大学で学ぶということ—エセ『主体性』に絡みとられないために」。日本の大学の歴史のレビューとオックスフォード大学での研究・教育経験との比較から日本の大学教育あるいは大学改革の裏にある問題点を鋭く突く内容でした。
「国立大学は、文部科学省の中央教育審議会の意向に沿った言葉を用いて自らのミッションを『主体的』に定義し、履行することが求められている」と説明する苅谷教授。もし大学側がこうした上からあたえられた言葉を用いて「主体的に」改革した気になっているとすれば、それはエセ「主体性」でないかと問題提起します。さらに苅谷教授は、こうしたエセ「主体的」な思考を「エセ演繹型思考」と名付け、現場や歴史から大学のビジョンを考える帰納型思考の必要性を説きました。

第2部では5つの分科会に分かれ、ファシリテーターを務める茨城大学の教員と、外部のゲストスピーカー、そして一般の参加者と一緒に議論を深めました。柴藤がゲストスピーカーとして参加したのは「残る『知』とは何か?」という壮大なテーマについて議論するグループです。公共哲学が専門の乙部延剛准教授とグラフ理論を専門とする松村初准教授がファシリテーターを務めました。

ディスカッションは、乙部准教授による「大学で学んだ内容それ自体は忘れてしまうこともあるが、『勉強習慣』といった知的な態度としての知はこの先ずっと残るのでは」という問題提起からはじまり、研究費問題の現状や「役に立つ研究」とはどういうことか、さらには成果を求められるスピードといった内容にまで及びました。
アカデミストとの関連で示唆的だったのが、選択と集中が求められるなかで、クラウドファンディングなどのサービスが研究を支える「オルタナティブな回路」となり、研究の多様性を維持するための仕組みのひとつとなる可能性があるのではという指摘でした。

他の会場では、「大学における「学び」とは何か?」、「いばらぎのイノベーションと雇用—大学は何ができる?」、「グローバル化ってしなきゃいけないんですか?」、「地域空間と大学—キャンパスは進化する?」といったテーマで分科会が行われていました。どれも地方国立大学のこれからを考えるうえで欠かすことができないテーマです。

各分科会での議論が終わると、最後に苅谷教授による質疑応答と全体総評がありました。
茨城大学教育学部の学生からは、教育学における理論と実践のバランスについての質問があり、それに対し苅谷教授は「実践の優れた理論化とさらなる実践との往復運動こそ必要だ」と答えました。声のトーンを上げて誠実に学生と向き合う苅谷教授の姿勢が印象的でした。
また、全体講評として苅谷教授は「年末の土曜日であるにも関わらず、これだけ多様な人が集まり『大学とは何か』を語る場は、普通ではない」とやや自嘲を込めて評し、「この『知の共同体』をつくりだすことこそ、これからも大学が担っていくべき重要な機能ではないか」と結論づけていました。

大学がステークホルダーを巻き込み、これからの大学について根本的に考えようとする機運を感じ、アカデミストもこの機運に応えてより大学、学術を盛り上げていきたいと思ったイベントでした。
この記事を書いた人

- 東京大学大学院学際情報学府修士課程。学部では1年次から哲学の原書テクストを精読するゼミに参加し鍛えられ、ベルクソン哲学で卒論を執筆。現在は人文社会科学がどこから来てどこへ向かうのかについて関心があり、特にそれと社会との交差点であるメディアに照準を定めて研究を進めている。