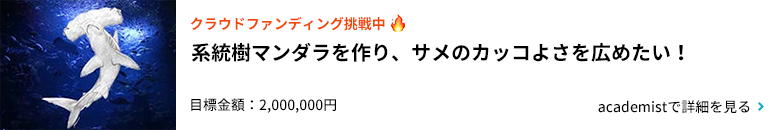DNAというものさしで生物種同士を比較する – 理化学研究所・工樂樹洋チームリーダーに聞く分子進化学者の役割とは
サメの知られざる進化の歴史を広く発信することを目指し、研究者やアーティストなどから構成されるチームがacademistのクラウドファンディングプロジェクト「系統樹マンダラをつくり、サメのカッコよさを広めたい!」に挑戦中だ。
この企画をアートとサイエンスにわけた場合、サイエンスの側においてカギを握るのは、生物がどのようなメカニズムでどのように多様化してきたのかをさぐる「進化学」。そのなかでも、DNAの塩基配列など分子の情報を用いる「分子進化学」への期待が高まっている。
では、進化の研究にDNA情報を持ち込むことには、どのような意味があるのか。どんな技術や考え方が大切なのか。世界で初めて公表された包括的な全ゲノム解析を行ったチームを率い、系統樹マンダラプロジェクトのメンバーである理化学研究所生命機能科学研究センターの工樂樹洋チームリーダーに伺った。
分子進化学は、DNAという“ものさし”で、生物種同士の相違点を把握する
——工樂先生は、生物の進化について研究されていますね。
私は、DNA解析によって、今までわかっていなかった生物の形や暮らしの成り立ちを解き明かせるのではないかと考え、さまざまな動物の研究を技術的にサポートする活動を続けてきました。一方、自らが主導する研究として、最近では軟骨魚類サメに着目して分子進化学的な手法を用いた研究を行っています。われわれ哺乳類の祖先をたどっていくと、サメの祖先と分かれたのは4.5億年ほど前と言われており、まだ大型生物の多様性に乏しかった海に住んでいた生物から進化してきたと考えられていますが、当時の生物の姿や暮らし方は、化石だけからでははっきりわかりません。
——先生のご専門である分子進化学は、そうした謎にどのようにアプローチしていくのですか。
生物の進化を理解するための第一歩は、生物種同士の相違点や共通点を詳細に把握していくことです。たとえば、サメの特徴を調べようと思ったら、サメ以外の別の生物を知る必要があります。分子進化学では、DNAの塩基配列、いわゆるATGCの並び方を比べるというアプローチで生物種同士の比較を繰り返し、それぞれがどういう関係にあるかを調べていくことで、時間軸に沿った変遷をとらえ、さらに遺伝子全体や染色体の部分へとスケールを拡げながら進化の道筋を解き明かしていきます。
——化石や現存する生物の形態を比較するような従来の進化学と比べて、分子進化学はどのような点に特徴があるのでしょうか。
DNAという、生物種のあいだで共通で対応関係がわかりやすい“ものさし”で評価することの意義はとても大きいです。たとえば、コウモリの翼は、指のあいだに膜が張られることによって形成されたことがわかっていますが、これを可能にしたのは、それぞれの指の関節の間隔が伸びたことです。では、進化の過程で4本の指に起きた関節の間隔が伸びるという現象は、4回の変化によるものと考えるべきでしょうか。もし、遺伝子のプログラムが1箇所だけ変わり、それが4本の指に現れたのだとしたら、生じた変化は1回だと考えることができます。形態を比較したり、化石を調べたりする従来の手法でこうした疑問に答えようとすると、どうしても恣意的にならざるを得ません。
一方で、DNA配列の比較では、生物種のあいだで対応する塩基の一致や不一致を淡々と数え上げていくことが基本です。分子進化学的手法を用いると、進化をより客観的、定量的に評価することができるのです。
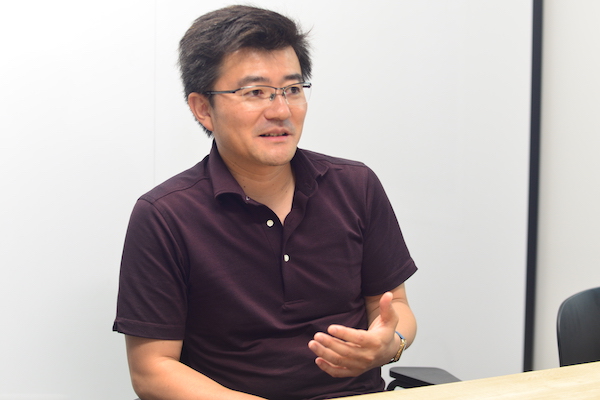
進化の系統だけでなく、その生物の「暮らし」もみえてくる
——生物種同士のDNA情報の相違点からわかるのは、進化の道筋だけなのでしょうか?
DNA情報を読み取ることには、生物がどんな暮らし方をしているのかを知る意味もあります。たとえば、サメの視覚を考えてみましょう。ジンベエザメは明るい水面近くでプランクトンを食べる一方で、ときには水深2000mまで潜ることが最近わかってきました。水面近くにおいてジンベエザメが光に依存して行動していることは、水族館における飼育下での観察からも知られています。では、深海ではどうでしょうか。最近読み取られたジンベエザメのDNA情報を精査して光受容タンパク質をつくる遺伝子を突き止め、ヒトの培養細胞で発現させたそのタンパク質にさまざまな波長の光を当てて反応を確かめたところ、深海でも届くと思われる青色の光をよく感知することがわかりました。だとすると、薄暗い深海でも光を頼りに、餌探しや交尾をしているのかもしれない。このように、暮らし方があまりわかっていない生物でも、DNA情報から暮らし方を推測することができうるのです。
——比べることで「暮らし」がわかるんですね。そうしたアプローチで自然界を眺めると、どんな世界観が描かれるのでしょうか?
私はよく「ヒトは、ちょっと変わった魚だ」と言っています。ヒトは、洗練された知能の有無でほかの動物と区別されることがありますが、DNAの配列という視点からみるとヒトと他の霊長類のあいだ、さらにはもっと視野を広げて、ヒトとサメのあいだであっても、大きな隔たりは感じません。現存の生物は、みな同じ時間をかけて少しずつDNAの情報の変化を蓄積しながら、生き残ってきた。ヒト以外の生物同士も、それぞれが個性をもつ尊い存在であることを、DNA情報を見ながらいつも感じています。「ヒトは自然の一部」「ほかの生物もリスペクトしよう」というメッセージを、直感的に伝えられるのが「分子進化学」かもしれません。

大切なのは「生体試料」「技術」「洞察」
——次に「分子進化学」の技術についてお聞かせください。ゲノム解析の精度を高めるためには、具体的に何が必要でしょうか?
大きく3つの要素があります。まず、情報を読み取りたい「生体試料」へのアクセス。次に、その試料からDNAの塩基配列を読み取る「技術」。そして、読み取った情報から新しい知見を得るための「洞察」です。
——ではまず、生体試料についてはどのように得ていますか?
まず、あたりまえのことですが、試料を得るために自然を乱さないことです。知りたい欲求があっても、生物の理解という名のもとに、命を過剰に犠牲にしたり、生態系を変えたりしてはいけません。
サメの場合、飼いきれない受精卵や健康管理のために採った血などの生体試料を水族館から分けてもらって、研究を行っています。研究室でサメを飼育したり、船を出して試料を取りに行くことも考えられますが、ノウハウがないと命を無駄にしてしまう可能性もあります。飼育はできるだけプロに任せておいて、問いに迫るための適した試料が得られるよう、そのプロと綿密な計画を練って、得た試料から最大限の情報を読み取ることに神経を注いでいます。
——ゲノム解析の技術はどのように高めていったのでしょうか?
もともと、私のミッションは技術部門のスーパーバイザーでした。いろんな研究者の多様なプロジェクトをサポートするうちに、私も含め研究室のメンバーのスキルが上がっていきました。自身がシーラカンスやヤツメウナギなどのゲノムを調べる国際コンソーシアムに関わった経験も貴重でした。権威のある学術雑誌に載るようなゲノム研究を間近に見ることで、DNA情報解析のデザインや得られた結果の伝え方、プロジェクトそのものの進め方などのノウハウも吸収することができました。
——試料を最大限に活かす技術が必要なのですね。
「完全ではない試料だけど、やっと手に入った」というときは、高い技術力が必要です。より良いデータを得るためには、技術をストイックかつロジカルに実践して、対策をしていくことが重要になります。また、DNA情報を読み取った後はコンピュータ上で作業を進めるのですが、より質の高い情報を得るために、細胞や染色体、そしてDNA分子というモノについて深く知ることが欠かせません。目の前にある試料の細胞や血はどういう状態なのか、DNA分子がその中にどんな状態で残っているのか把握できること。生体試料の採取から運搬、保存、解析まで妥協なく進める実験のスキルが必要です。
——得られた情報を生物学につなげる洞察とは?
たとえばサメの研究なら、「サメの何がわかっていないのか」という問いの洗い出しが大事になります。これまで軟骨魚類のサメの進化は、あまり調べられてきませんでした。マウスやゼブラフィッシュなど伝統的なモデル生物が含まれる生物群と異なり、手ごろな実験動物がないので、実験志向の研究者に避けられてきたということは明白です。でも、実験しにくいから知らないままでよい、なんていうはずはありません。だから今、学生のときから持っていた興味を呼び覚まし、サメの体の形や暮らしの成り立ちを解き明かすための研究にも取り組んでいます。いままで知られていなかったことで、とくにゲノムを見渡しているからこそ切り込めるような着目点、これを突き詰めたいと思っています。

進化を知ることで、進化以外の問いに答える
——最後に、分子進化学の現在とこれからについて、お話を聞かせてください。
分子進化学の理論は、すでに1980年代に基礎の部分ができあがっていました。近年、DNA解析技術が進歩したおかげで、ゲノム規模のDNA情報にその理論をあてはめ、生物進化を分子のレベルで深く調べることができるようになりました。その視野は、遺伝子からゲノムへ、そしてDNA配列から核内にあるDNAの3D構造のような、より高次の情報へと広がっていきます。得られるようになったDNA配列などの情報は、研究者、さらには人類全体の財産だと思っています。
——「財産」とはどのような意味でしょう?
多様な生物のDNA情報は、いろいろな生命現象を理解するために役立ちます。地球にいるすべての生物のゲノムは、自然の進化が生んだ財産です。データを読み取る前に絶滅してしまえば、消えてしまうかもしれません。生命科学は、これまで別々の生物や分野で蓄積された知識を有機的に統合していくことが重要な時代になりつつあります。種をまたいでその知識を繋げる鍵は分子進化学であり、最終的には、それが「進化以外の問いに答える」ことに寄与するはずです。
——「進化以外の問いに答える」とは?
わかりやすく説明できるのは、やはり医学への活用でしょうか。たとえば免疫のメカニズムを調べるとき、まずマウスで研究して、得られた知見をヒトに転用するのが一般的です。でも、マウスとヒトは5000万年以上前に分岐した間柄。違うところはたくさんあります。その違いがDNAレベルで詳細に把握できていれば、「マウスでのこの知見はヒトにも適用できる」とか「どんな動物で実験すればヒトへの効果がより正確に推測できる」などといったことを考慮できるのです。
分子進化学の世界観が、医学をはじめとするほかの分野に浸透していくことで、生命科学全体のより深い理解につながっていくのではないかと考えています。
——分子進化学で得られた生物種同士の“距離感”のようなものが、さまざまな種を対象に進められている生命科学をつなぎあわせ、発展させる土台になるということですね。
まさに、そのとおりです。「生物がどう進化してきたのか」を調べるとともに、「生物種同士がどのくらい離れていて、どこが違っているか」を、進化の時間軸を念頭において、ひとつひとつ“マッピング”していくことも分子進化学の使命です。ひとつの生物について調べたときに、ほかの生物種との比較に基づいて理解するのはとても重要なことですが、これを定量的かつ客観的に行うには分子進化学の専門的な手法が必要です。専門的な手法に基づけば、時間のわりにDNA配列の変化が速いゲノムの部分を見つけたり、生物のあいだのDNA配列の変化スピードの違いを知ることもできます。サメを調べた結果、DNA配列の変化のスピードが際立って遅いことがわかりました。これが、寿命やゲノムサイズ、そして生息環境と関わっているか、興味を持っています。他の生物でも成り立つような「生命現象のペース」を決めるしくみを解き明かす糸口になるかもしれません。分子進化学は地味かもしれませんが、いろいろな研究分野が細分化されていくなかで、その隙間をつなぐ役割を担うことができると思っています。
——おもしろいですね!
サメを研究するのは、生命全体の進化をより高い解像度で把握するために、欠けていたピースを埋めるようなもの。分子進化の考え方が、生命科学全体の必須ツールとしてもっと浸透することを目指しています。
工樂樹洋氏 プロフィール
理化学研究所生命機能科学研究センターチームリーダー。1976年奈良県奈良市生まれ。1999年に京都大学理学部卒業。2005年京都大学より博士号(理学)取得。その後、理化学研究所研究員やコンスタンツ大学(ドイツ)の教員を経て、2012年より現職。専門は分子進化学、ゲノム情報学、発生生物学。
この記事を書いた人

- フリーランス科学コミュニケーター 兼 アーバン・サイエンス・ラボ主任研究員。星が好きなのに農学部へ進み、アジア横断の旅行記を書くのが楽しくて新聞記者に。日本科学未来館の科学コミュニケーターを経て、現在は設計事務所でまちづくりを研究しながら、「科学する」「伝える」「対話する」「学び合う」を軸に個人事業を拡大中。