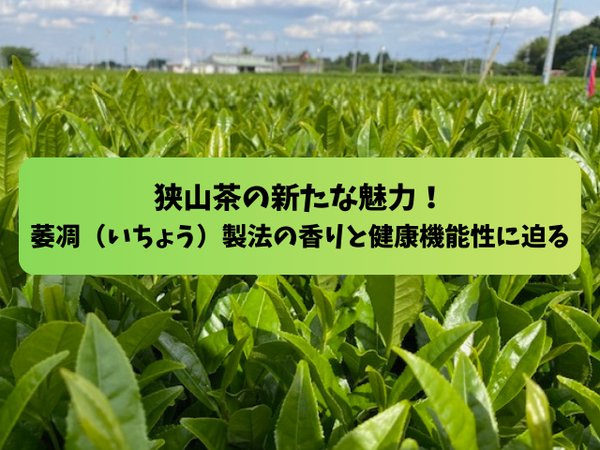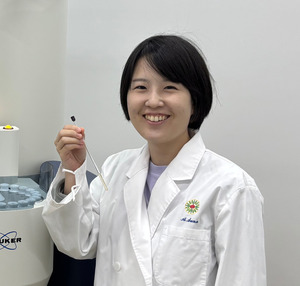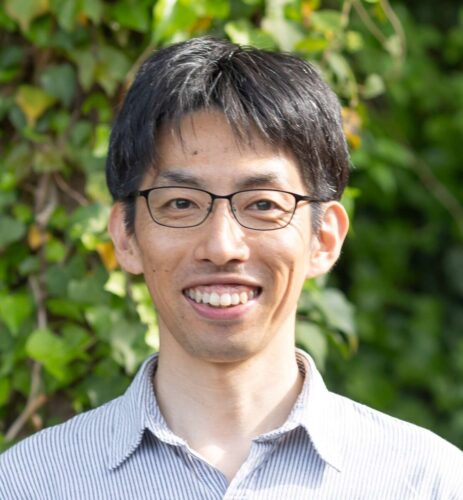
挑戦期間
2022/11/01 - 2027/10/31
最終活動報告
2026/01/30 20:05:13
活動報告
70回
サポーター
35人
経過時間
2022/11/01 10:00:00
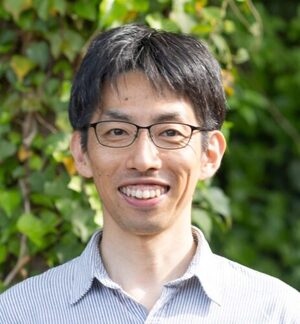
#49 所属している研究部門のウェブサイトが公開されました
社会的共通資本(Social Common Capital:SCC)に関する研究部門が、京都大学の成長戦略本部 Beyond2050というイニシアチブの下に、この4月からできました。
ウェブサイトが公開されましたので、よければご覧ください。
https://www.beyond2050.iac.kyoto-u.ac.jp/scc-center/
メンバーの中に私も入っています。
ht
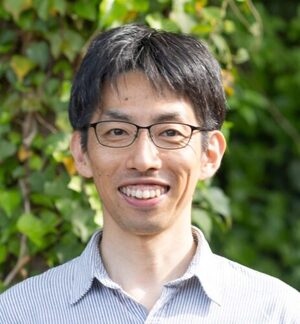
#48 寄付募集マーケティング戦略の「実行部分」が難しすぎる、という問題
研究をしていて非常に楽しいのは、「おおっ!!!」という論文に出会った時です。
最近は、この論文でそんな瞬間を体験しました。
Morgan, N. A., Menon, A., Jaworski, B. J., & Musarra, G. (2025). Marketing strategy implementation: Why is it so hard? Journal of Bus
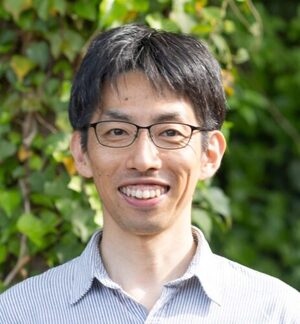
#47 高齢層と寄付についての研究をご紹介
最近、風邪の治りがめっぽう悪く、中高年に足を踏み入れているな…と感じる渡邉です。
さて今日は、いくつか高齢層の方々と寄付の関連について、研究をレビューしていこうと思います。
研究への寄付募集、特に高額寄付の募集を考える時に、保有する資産額が多い傾向のある高齢層の方々は、非常に重要な存在だからです。
寄付行動は幸福につながる(Dunn et al., 2020)といわれておりますが、
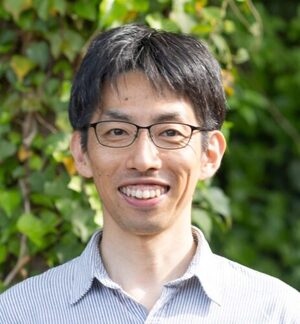
#46 寄付の根本問題と、寄付募集の根本問題
今年度は、幸いにして常勤の特定准教授として大学で研究できる環境があります。
といっても、多くの教員の方々が担われている「教育と研究」という役割ではありません。
「実務と研究」を行う立場にあります。
ですから、やはり実務にとってインパクトのある研究をしたいと考えています。
実務にとってインパクトを生む研究には、「そもそも論」に立ち返るようなテーマが重要です。
言い換えれば
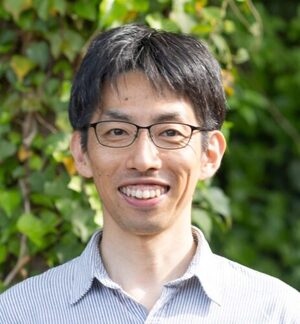
#45 寄付市場を理解するために―Z世代の向社会的消費行動
京都大学には学際的な研究を行うための「ユニット」制度があり、様々な部局から近しい関心を持った研究者が集まって研究交流を深めています。
先日、「こころの科学ユニット」が開催する「こころの科学研究者⼤交流会 2024年度冬の陣」があり、せっかくなのでポスター発表をしてきました。
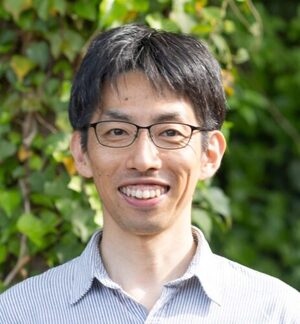
公的研究費申請の結果が届きました
本プロジェクトをご支援くださっているみなさまへ
昨年、本プロジェクトでこれまで得てきたデータや知識を基に、
「教育・研究機関の寄付募集能力の構築過程と寄付市場の選好に関する研究」
というテーマで科研費(若手研究)に申請しました。
(40歳過ぎて若手なの?という声も聞こえてきそうですが、博士号取得後8年未満を指すので私はまだまだ若手です…)
内容については、以前のご報告に
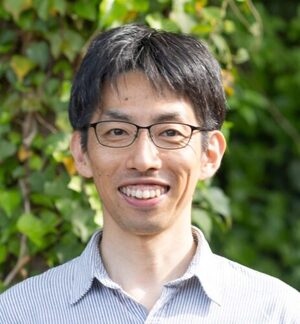
研究への寄付募集の成否を決める要因と本プロジェクトの継続について
サポーターのみなさま
先日、アカデミストさんのOpen academia Lecturesで、本プロジェクトを通じて行っているアクション・リサーチの結果のさわり部分を進捗報告させていただきました。
開催レポートが下記URLにアップされているので、ご確認いただければと思います。
https://note.com/academist/n/n7fa2215aaaab
この記事では、
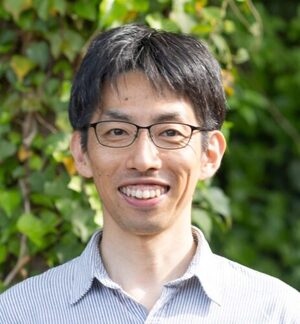
Open academia Lectures登壇(サポーターの方は無料です!)
今度の1月17日、アカデミストさんが行われているOpen academia Lectures #4でお話をすることになりました。アーカイブ視聴あり、Discordへも参加できるそうです。
お題は「“研究への寄付”をどう広げるか」というもので、本プロジェクトを通じて得てきた知見を共有する部分もありますので、よければぜひご参加ください!
本プロジェクトのサポーターの方は無料でご参加いただけま
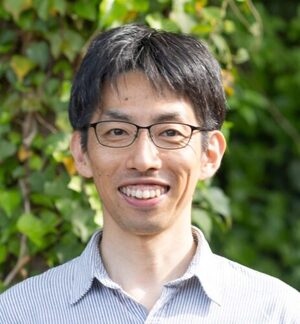
【訂正あり】#44 Donor-Advised Fundsと経済格差
前回の活動報告について、最終的な修正前のバージョンの原稿をアップしてしまっていたことが分かりましたので再投稿します。申し訳ありません。何度も確認したものの、まだ誤字が残っていないか心配ですが…。
前回のものは、削除をacademistさんにご依頼しておきます。
**********
日本の大学の10年後をファンドレイジングの視点から考えるにあたり、非常に重要なテーマがDonor-Advis
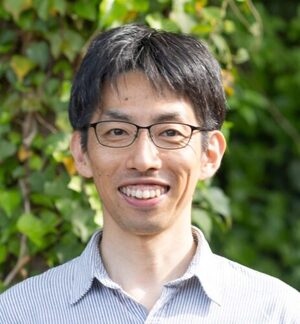
#43『寄付白書2025』の調査に参加/法人寄付について話します
研究への寄付募集を考えるとき、非常に重要なアクターが企業や財団などの法人からの支援です。
ところが、既存の寄付研究はどちらかというと心理学や経済学を使って「寄付をする個人」という対象に迫ったものが多いのです。
私のように、「寄付を募る側」の研究や、「寄付をする個人以外の主体」の研究は相対的に少ないです。
そのような中、寄付研究促進委員会という委員会において、
『日本の企業寄付を「