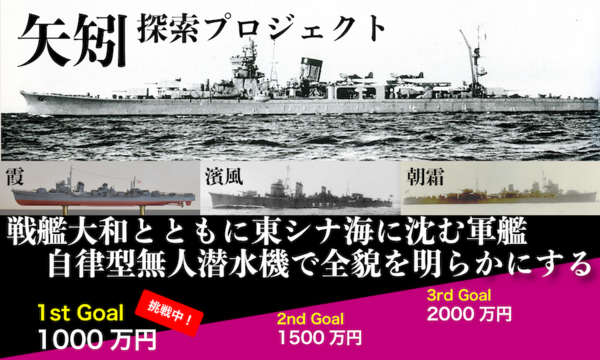待井 長敏
挑戦期間
2023/09/05 - 2025/03/31
最終活動報告
2025/03/18 15:23:51
活動報告
24回
サポーター
21人
経過時間
2023/09/05 10:00:00

異分野交流は遊びか?「目的への抵抗」から考える真剣な遊び
みなさんどうも、待井です。
今日は、私の好きな國分功一郎先生の「目的への抵抗」[1]を参考に、タイトルにある話題を取り上げて私の考えを書こうと思います。
現在東大の教授となった國分先生は、実は以前少しだけ東工大(現科学大)に在籍し、哲学の授業を行っていました。私は幸運にもその短い在籍期間の授業をたまたま受講していて、感銘を受けました。先生の気さくな性格と、難しい哲学の話を噛み砕いてわかりやすく話す姿は、今でも印象に残っています。その尊敬する先生が私が以前から考え、悩んでいたことを本で言及してくれていたので、今日はそれをみなさんにも共有しようと思います。
さて本題ですが、ここでは異分野交流のワークショップと「遊び」の概念の関係性について、もっと言えば「遊び」の一環として行う異分野交流について考えてみたいと思います。あえてカギカッコで括ったのは、忙しい研究者を集めてやる会に「遊び」という言葉をあてがうのは如何なものかという人に一旦待ったをかけるためです。今日の記事で、ここでいう「遊び」が私たちが異分野交流を、ひいては研究者人生を楽しむために重要な概念だということを理解していただきたいと思っています。
ちなみに本書で國分先生が遊びと政治の関係性について述べる際には、以下のように述べています。
「遊びなどというとふざけているのかと思われるかもしれません。(中略)しかし、そもそも勘違いしてはならないのは、遊びは真剣に行われるものだということです。砂場の山作り、トンネル作りも、この講話も、文化祭の活動も、真剣に行われるから楽しいのです。充実感があるのです。」 (目的への抵抗 p179−180)
私も全く同感です。私たちはもっと真剣に遊ぶことについて考えるべきなんじゃないかと思います。
ただ、真剣に遊ぶとは一体どういうことでしょうか?
國分先生は遊びを「目的によって開始されつつも目的を超え出る行為」(同書p179)として定義しています。
例えば、文化祭で出し物を決めるために話し合いをするとしましょう。これは文化祭に参加するという目的のために行われる行為です。ただ、その目的から始まった話し合いもみんなでアイディアを出し合ううちに、ワクワクして楽しくなってくる瞬間があることもあると思います。その瞬間はもはや文化祭に参加するという目的を超えて、その過程そのものが楽しくなってると言えるでしょう。このような瞬間が、國分先生のいう遊びです。
研究では目的がとても強い力を持っています。自身で設定した研究目的を正しく遂行する能力は研究を行う上で必要不可欠な能力であると言えるでしょう。しかしながら、その目的を超えて見つかった思いがけない発見こそ、重要なのではないでしょうか。実際に遊びと創造性やイノベーションとの関連性は、様々なところで言われています[2]。それに、そうしたセレンディピティー的な発見を目的遂行から逸脱するがゆえに蔑ろにしていては、研究自体の楽しさも失われていってしまうのではないでしょうか。だから私が言いたいのは、研究者はもっと真剣に遊ぼうということです。
私はこの遊びの最たる例として異分野交流を捉えています。
なぜかといえば、異分野と交わることは今あなたが持っている研究目的を容易に逸脱へと導いてくれるためです。専門分野の基盤を共有していない異分野の人に対して自分の研究を説明するとき、まずは自分の研究目的を内省する必要があります。そしてその自覚を持って他の分野との比較が行われます。アナロジーの発見や、相違点の気づきを通じて、お互いの立場の違いを理解していきます。最終的に相手の研究を自身のフレームで捉え直したり、相手の研究を鏡のようにして自身の研究を捉え直したりする、リフレーミングが起こります。この過程はまさに目的からの逸脱を推進してくれるのではないでしょうか?だから異分野交流こそ研究目的の逸脱、言い換えれば真剣な遊びへと誘ってくれると私は思っています。
そして遊びから生まれたその余剰分こそが、世界中で、あなただからできる研究(独自性)とあなたしか知らない視点(新規性)を生み出すのではないでしょうか。
余談ですが、異分野交流はどんなに考えて設計しても、うまくいく会と、退屈に終わる会があります。これまでそのうまくいくとは何かよくわからず、なぜかわからないけれど、楽しかったとか、今回はつまらなかったとか、ぼんやりと判断していました。ですが、結局それは参加者が参加当初もっていた目的を超えられたかどうかなのかなと今は思います。
ここまで話をしてきましたが、実は異分野交流を「遊び」として捉えるかどうかは実践者の間でもバラバラです。例えば、京大で「総人のミカタ」という異分野の人を交えた模擬講義を経験した、ある方は著書[3]で次のように言っています。
「自分にとって「ミカタ」が楽しい場として機能しているかと言われると、おそらくそうではない。むしろしんどい場です。来たくない日のほうが多い。「ミカタ」に来るメンバーは仲のいい人が多くて、一緒にご飯にいくのはもちろん楽しいし、お酒も飲めたらうれしいのですが、この場に自分が来ると、「子どもの発達」という研究分野を代表しなければいけないし、自分がなぜこの研究をしているのかをいちいち見直さないといけない。そういうことを迫られる場なので結構しんどい。来たくないなと思うけれども、でも大事だと思うので来ているということがおそらく答えかと思います。 (〈京大発〉専門分野の越え方: 対話から生まれる学際の探求 p87)
上述の実践者としての赤裸々な気持ちは私もわかります。自分が言ったことがその分野の意見として捉えられてしまうがために、適当なことは言えず、交流の際中はとても気を使いますし、疲れます。それでも異分野と触れ合う中で何か得るものがあって、そのために来るというのは、とても崇高な目的です。ただ私としてやはり、その目的さえをも超えていきたい。異分野の人との対話の中に心から熱中するやりとりをうみたい。その時、交流体験は何か真剣な遊びとして、より大きな意味を持つんじゃないかと思っています。
まとめます。今回は異分野交流を國分先生の「遊び」の概念を借りて捉え直してみました。確かに研究は国や企業から少なくないお金をいただいて目的を遂行する大変真面目なものです。けれども本当に独創的で新規な研究というのは単なる目的の設定と遂行の中では生まれず、それをはみ出して、真剣に遊んだ時に生まれてくるのではないかと思っています。そして、異分野交流は自分の研究目的から解き放たれ、自由に対話することができる場として重要な機会を生んでいるのではないでしょうか
[1]目的への抵抗 (新潮新書) 國分功一郎 2023/4/17
[2]なぜイノベーションに「遊び心」が必要なのか? 安斎勇樹 2019/5/16 https://note.com/yuki_anzai/n/nac85a7b88919
[3]〈京大発〉専門分野の越え方: 対話から生まれる学際の探求 2023/3/31 萩原 広道ほか

0人が支援しています。
(数量制限なし)

0人が支援しています。
(数量制限なし)

0人が支援しています。
(数量制限なし)