目標金額を達成しました!

皆様のご支援で、目標を達成いたしました。予想以上に多くの方からご支援を頂戴し、誠にうれしく存じます。ご支援いただいたお金は、所定の計画通り2019年度夏のドイツでの在外調査費用として活用させていただく予定です。
リターンとしてお約束している単著は、現在初稿校正が終了しており、遅くとも2019年本年中には出版できるよう準備しています。また、サイエンスカフェ(5月上旬)、ドイツ軍事史講義(夏を予定、3回)につきましても、アカデミストの担当者と相談しながら、日程、会場など調整させていただく所存です。
皆様のご支援のおかげで、開始から四日と想像以上のスピードでクラウドファンディングに成功することができました。ご支援ありがとうございました。
academist スタッフからの一言
日独の軍事史を紐解き、近現代史の新たな視座を開拓する

荒井俊
物心がついたときに経験した冷戦の崩壊
私が研究している軍事史は、「広義の軍事史」とも呼ばれ、社会全体において軍隊が果たした役割を、多角的な視点で研究する学問分野です。私はとくに、軍隊が「どのようにして」社会に影響を及ぼしていったのか、ということに興味を持って研究を進めています。
私がドイツ近現代史に関心を持った理由は、同時代の体験にあります。私は物心がついたころに1989-1990年の冷戦の崩壊があり、日々歴史が書き換えられていく瞬間、ドイツ再統一を目にした世代です。私はまだ小学生でしたが、ちょうど新聞や歴史書に関心を持ちはじめていた時期で、歴史の変化を目の前に示されました。ドイツに強い関心を持った理由はこのことと関係しています。そのあと、ドイツの近現代の歴史に関心を持つなかで、ドイツという国が数多くの戦争とかかわっていたことから、戦争や軍隊を客観的に研究する軍事史に興味を持つことになりました。

近現代史を読み解くうえで欠かせない軍事史
もともと、ドイツ近現代史の研究のなかでも、軍隊や戦争の研究は長らくタブー視されていた傾向がありました。これはドイツが20世紀のふたつの世界大戦の直接的な責任を担う立場であったこと、とくに第二次世界大戦を引き起こした国であったことに起因しています。ナチス・ドイツの世界観のなかで、戦争や軍隊を賛美する世界観が大きな意味を占めていました。このことは、第二次世界大戦後、歴史学の研究対象から、軍事史や戦争の問題を遠ざけることになりました。
ただ、冷戦の終結以降、軍隊や戦争を歴史学の検討対象にはしないというタブーはなくなってきています。いま軍事史は新しい社会学や文化研究と結びつくなかで、近現代史を見ていくうえで欠かせないものになっています。戦争は、戦争の前後の社会全体を根本的に変えていきます。徴兵制によって国民を軍隊に統合していくシステムもまた、社会の仕組みや人々の考え方を変えるうえで重要な影響を与えました。こうした変化を捉える軍事史は歴史学のなかでも多くの関心を集め、国際的に関心が持たれています。

日本とドイツの人々は戦争をどのように受け入れようとしていたのか
私は、これまでドイツ帝国の軍事著述家たちの著作を分析してきました。とくにドイツ帝国の成立から第一次世界大戦直前(1871-1914年)に書かれた一般兵役義務に関する文献や論文から、当時の議論のなかで自国の軍隊システムを高く評価する主張が、次第に変化していく様子を明らかにしました。とりわけ、将来起こりうる戦争への対応策が求められ、さらにこれに対応するために社会を軍隊のシステムに合わせようとする変化を論じました。今までの研究では、戦争勃発の過程に関する研究は、外交や戦争計画といった政治家や軍の責任者の役割の分析が中心でした。私の研究は、世論に強い影響を与えるオピニオンリーダーたちがどのような考えの変遷を経て、自分たちの専門家の論理を社会に反映していったのかを知るうえでのモデルケースになると考えています。
このような状況はドイツだけでなく、ドイツと強い関わりがあった日本の近代史を見るうえでも参考になります。日本の近代化ではドイツは重要なモデルのひとつでしたし、とくに陸軍での影響力の大きさはよく知られています。戦前の「軍国主義」といわれた状況、日本の軍人がドイツの軍事文献の影響を受けていたことなどは、これまでの研究である程度明らかになっています。
しかし、第一次世界大戦以降の日本の軍人がドイツの軍事文献でなにを読み、そこからなにを吸収していったのか、またドイツの軍人たちが日本をどのように見ていたのかについてはまだまだ議論の余地があります。この点でひとつの尺度となるのが、ドイツの軍事思想家 カール・フォン・クラウゼヴィッツの『戦争論』です。本書を活用しつつ分析することは多くのメリットがあります。『戦争論』は現在でも読まれている文献で、その論理を把握することは現実の歴史を分析するうえでいまだに非常に有益です。この研究が進めば、戦争という困難な状況に際して、日本とドイツの人々が戦争をどのように受け入れようとしていたのか、どのような語り方が戦争を論じるうえでありえたのかが明らかになると考えています。

研究費サポートのお願い
以上のような調査、研究のためには、ドイツ各地の図書館、文書館、研究所へのアクセスが欠かせません。今回は研究対象を絞るなかで、1か月程度の滞在期間のなかでできるだけ多くの史料に目を通したいと考えています。このため、クラウドファウンディングでご支援いただいたお金はドイツへの往復の飛行機運賃、ドイツ国内の交通費、そして当地での宿泊費用、文献資料の購入などで活用したいと考えております。
今後の目標としては、資料調査を通じて従来明らかになっていなかった史料状況を確認し、ドイツ帝国からナチ時代に軍人向けや一般向けに出版されていた著作や雑誌のなかでドイツ側が日本の軍隊をどのように見ていて、それがどう表現されていたのかに着目します。

挑戦者の自己紹介

中島浩貴
中島浩貴(なかじま ひろき、博士〔学術、早稲田大学〕)と申します。現在、理工系大学である東京電機大学理工学部講師をしています。普段は理工系大学の教養(共通教育群)の教員として、歴史学、欧米文化研究、ドイツ語などを教えています。専門は歴史学(ドイツ近現代史)で、とりわけ軍事史です。著作として、共編著『ドイツ史と戦争』彩流社、2011年。共著『クラウゼヴィッツと「戦争論」』彩流社、2008年。共著『技術が変える戦争と平和』芙蓉書房出版、2018年。共訳に、トーマス・キューネ、ベンヤミン・ツィーマン編著『軍事史とは何か』原書房、2017年などがあります。世界史研究会や日本クラウゼヴィッツ学会などでも積極的に活動しています。
研究計画
| 時期 | 計画 |
|---|---|
| 2019年1月 | クラウドファンディング挑戦 |
| 2019年3月 | クラウドファンディング終了 |
| 2019年4月〜7月 | 日本で所蔵されている史資料の確認 |
| 2019年8月〜9月 | ドイツに所蔵されている史資料の確認、複写など |
| 2020年~2021年度 | 調査した史料を用いて、学会・研究会での発表を予定 |
| 2020年~2021年度 | 調査した史資料を用いた論文執筆 |
リターンの説明
研究および研究活動についての詳細な進捗状況をレポートにまとめてお送りします。

研究報告レポート
14人のサポーターが支援しています (数量制限なし)
近く出版予定の著書『国民皆兵とドイツ帝国 一般兵役義務と軍事言説 1871-1914年』彩流社、2019年(予定)をサイン入りでお送りします。

サイン入り著書 / 研究報告レポート
41人のサポーターが支援しています (数量制限なし)
サイエンスカフェにご招待いたします。日時は2019年5月上旬で、場所は東京都内を予定しています。当日は「ドイツの軍事史研究の可能性」についてお話させていただきますので、ご参加をお待ちしています!
※当日ご参加いただけない場合には、後日資料を共有させていただきます。)

サイエンスカフェ / サイン入り著書 / 研究報告レポート
7人のサポーターが支援しています (数量制限なし)
近く出版予定の著書『国民皆兵とドイツ帝国 一般兵役義務と軍事言説 1871-1914年』彩流社、2019年(予定)、私が共訳したトーマス・キューネ、ベンヤミン・ツィーマン編著『軍事史とは何か』原書房にサインを入れてお送りします。また本研究成果を発表する際の謝辞にお名前を掲載させていただきます。※研究成果をまとめられるよう努力いたしますが、論文の掲載に至らない可能性もございますこと、ご承知おきいただけますと幸いです。

サイン入り著書(2冊) / 論文謝辞 / サイエンスカフェ / 研究報告レポート
1人のサポーターが支援しています (数量制限なし)
大学での講義(早稲田大学、東京電機大学など)や日本クラウゼヴィッツ学会での講演、学会報告などでお話ししたエッセンスをまとめて合計3回(60分×3)の講義をいたします(2019年夏、日時は後日調整いたします)。ドイツ軍事史の全体説明、近年のドイツ軍事史の状況、クラウゼヴィッツ研究などについてわかりやすく説明いたします。

ドイツ軍事史に関する講義(全3回) / サイン入り著書(2冊) / 論文謝辞 / 研究報告レポート
4人のサポーターが支援しています (数量制限なし)
5万円までのリターンに加え、共著『「技術」が変える戦争と平和』芙蓉書房、2018年を送らせていただきます。
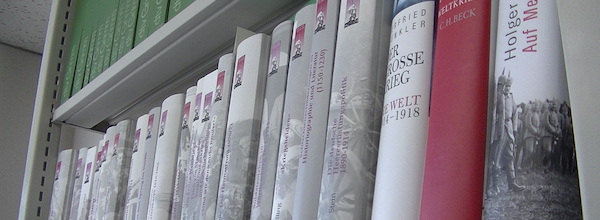
サイン入り著書(3冊) / ドイツ軍事史に関する講義(全3回) / 論文謝辞 / サイエンスカフェ / 研究報告レポート
3人のサポーターが支援しています (数量制限なし)
当サイトは SSL 暗号化通信に対応しております。入力した情報は安全に送信されます。
研究報告レポート

14
人
が支援しています。
(数量制限なし)
サイン入り著書 他

41
人
が支援しています。
(数量制限なし)
サイエンスカフェ 他

7
人
が支援しています。
(数量制限なし)
サイン入り著書(2冊)、論文謝辞 他

1
人
が支援しています。
(数量制限なし)
ドイツ軍事史に関する講義(全3回) 他

4
人
が支援しています。
(数量制限なし)
サイン入り著書(3冊) 他
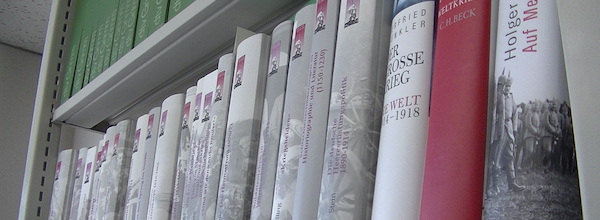
3
人
が支援しています。
(数量制限なし)




