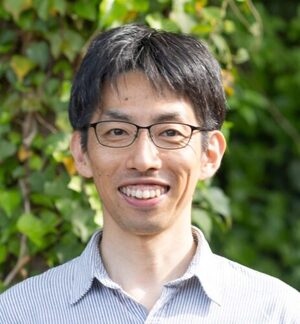Challenge period
2022-11-01 - 2026-08-31
Final progress report
Wed, 29 May 2024 15:07:21 +0900
Progresses
20 times
Supporters
8 people
Elapsed time
Tue, 01 Nov 2022 10:00:00 +0900

ご無沙汰しております。色々と進捗がございました。
大変ご無沙汰しております。しばらく更新していなくて、本当に申し訳ございませんでした。
実は2~4月で色々と進捗がございました。
大きなのは助成金(2件)の獲得と、ひろしまUnicorn10での最優秀賞。
なかなか評価されにくい材料分野が徐々に脚光を浴びてきて、嬉しく思います。
https://www.materialgate.com/news/
実は、オフレコ情報になるのですが

新年あけましておめでとうございます。
元日より大変なニュースが続いておりますが、今は自分自身が出来ることを一生懸命頑張っていこうと思っています。改めて本年も宜しくお願い致します。
さて、昨年は本当に内容が濃い一年でした。
ひたすら走り続けて、振り返ると色々と記憶が曖昧ですが、創業&新規事業の立ち上げ
更には研究開発で非常に多くの方に出会い、多大なご支援を頂きました。
特にacademistのサポーター様や関係者の皆様には大変

本格的な事業化&製品開発を開始致しました。
サポータの皆様、いつもご支援有難うございます。
改めて活動更新が毎度滞りがちで、申し訳ございません。
今回は表題の件について、あまりオープンになっていないことを記載してみようかと思います。
①メモリデバイス開発パートナーが見つかりました。
➣ 事業進捗としてはかなり大きく、実用化に一歩近づいたイメージです。
➣ 今後我々が開発を行うにあたり、キーワードになってくるのはメモリの「

時間が空きましたが、、、Google for Startupsに登壇していました
御支援者の皆様、活動報告が空いてしまい、大変申し訳ございません。
会社設立後、色々と忙殺されており、諸々手つかずの状態でした。。
少し遡るのですが、6月の活動報告です。
会社設立申請の翌日6/20に、掲題イベント Google for Startups Hiroshima Startup Summit の登壇依頼を頂戴しました。
イベント名だけでも十分なインパクトですが、なんとG7からの

広島大学発スタートアップを設立しました!!
サポーターの皆様
いつも大変お世話になっております。
掲題の件にて,先日6/19に広島大学発スタートアップとして「株式会社マテリアルゲート」を創業致しました!
事務処理でバタバタしており、連絡が遅くなり恐縮です。
こちらの月額クラウドファンディングに加え,先日チャレンジしたスポット型を機に引き合いも増えて、事業としても非常に良いスタートを切れそうな状況です。
まだまだスタートラ

academist Prize 2期イベントにてダブル受賞を達成しました。
御支援者の皆様、大変お世話になっております。
先日の活動報告(https://academist-cf.com/fanclubs/271/progresses/2824?lang=ja#documentBody )でも申し上げました掲題のイベント「若手研究者と考える『基礎研究の社会実装』」にて、企業賞(日本の研究 .com 様)とオーディエンス賞のダブル受賞を頂戴しました。
素材分野とい

academist Prize2期イベント&半年間の振り返りと活動報告について
ご支援者ならびにご関係者の皆様、いつも大変お世話になっております。
掲題の件につきまして、月額支援型プロジェクトを開始してからの活動報告を纏めたいと思います。
まず私自身の究極のミッションから改めて確認させて頂きます。
【ミッション】日本の素材・化学分野を学術・産業共に盛り上げる
私自身、修士課程修了後に社会人経験を経て、博士課程に進学していることもあり
研究成果で社会貢献すること

スポットチャレンジ!大学発スタートアップを起業します!
月額支援サポーターの皆様、いつも多大な御支援ありがとうございます。
この度、新たにスポット型のクラウドファンディングに挑戦することに致しました。
https://academist-cf.com/projects/291?lang=ja
こちらの月額チャレンジの計画にも23年度上半期での起業を記載しておりましたが、諸々の目処が立ちましたので6月の起業を目指して新たなスタートを切るつもりです。

品川ビジネスクラブ「ビジネス創造コンテスト」で優秀賞を頂いておりました
NEDO TCPでJST賞を頂いた割と直後、表題のコンテストでも受賞を頂きました!!
実はこのコンテスト,個人的に初となる「賞金」を頂けるイベント!!
しかも全く関係者もいない場で,結構倍率も高かった(書類選考で200件,最終プレゼンで約10チーム)での評価でしたので、非常に嬉しい結果となりました。
しかも品川のコワーキングスペースも使わせて頂けるということで,特典もいっぱいです。

第4回アカデミスト起業研究会オンラインイベントに登壇します!
活動報告が滞っており申し訳ございません。
2月から色々なイベントに参加しており、お恥ずかしながら色々と手が回らなくなっておりました。
それらの活動内容については、改めて報告させて頂きたいと思います。
さて直近の活動予定なのですが、4/5(水)に18時より掲題のイベントで登壇させて頂きます。
参加フォームは下記です。https://qr.paps.jp/WxD1q
まだ何も成し遂げて