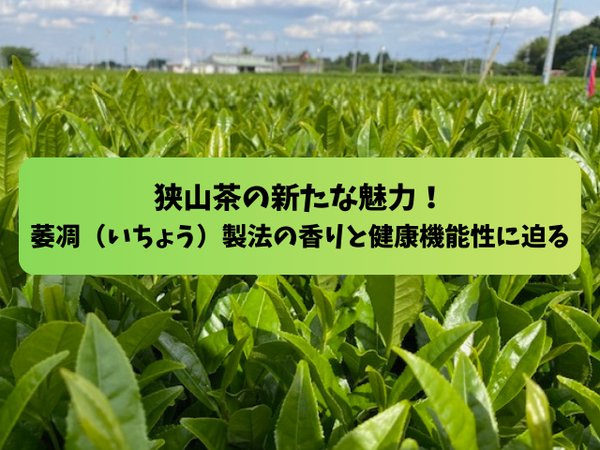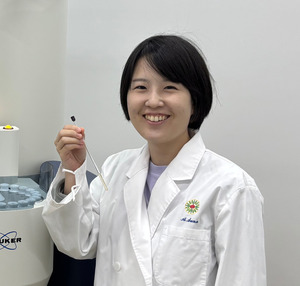今月の報告
更新遅くなりまして、大変申し訳ございません。前回もお知らせしましたが、所属先が移動となりました。研究する領域や内容は相変わらず協力の進化です。
今回は進化ゲーム理論という、ゲーム理論に進化の概念を取り入れた枠組みを用いて明らかにされている協力の進化メカニズムについて1つ紹介したいと思います(Nowak, 2006; Rand & Nowak, 2013)。
互恵的メカニズム①「血縁淘汰理論/

今月の報告
前回は社会的ジレンマと経営学との関連を紹介し、幅広い分野で扱われている研究トピックであることを紹介しました。今回は協力の進化というトピックを研究するにあたり、それを後押ししてくれる?風呂敷を広げるといいますか、我々はこーんな重要な研究をしているんですよ!という時に使う売り文句のような内容を紹介します。
社会的ジレンマ状況(個人と集団の利益対立)にさらされているにもかかわらず、人間をはじめとした

今月の報告
今回は、関連研究紹介第2弾です。社会的ジレンマというトピックと経営学との関連を紹介します。
社会的ジレンマ問題は経営学の分野においても重要な課題であり、ナレッジマネジメントがその一例です。組織内における従業員間の情報共有「ナレッジマネジメント」は、組織全体にとって大きな資産となりえます。しかし、情報を提供する個人にとってはコストを伴い、他の組織メンバーの情報にフリーライドする要因が構成員には存

前回までの研究の結果は前にも載せたかもしれませんが、オンライン学術誌であるPLOS ONEに掲載されています。ご興味ありましたら是非ご一読ください。
今回から、私がこれまでに行ってきた研究の関連研究を紹介し、私の研究の位置づけをとらえていただければと思います。私は本年3月をもって所属大学院を卒業する見込みでありますが、4月より筑波大学大学院博士後期課程へ所属を移し、研究を継続していきます。研究

前回までのおさらい
社会的ジレンマにおける協力を説明するメカニズムの一つが「間接互恵性」
その善悪の判断は規範と呼ばれ、最も単純な規範はイメージスコアリング(Nowak & Sigmund, 1998)
イメージスコアリング・・・観察している人が、協力していれば善、裏切れば悪
イメージスコアリングは、完全な非協力者による誤差や侵入に弱く、進化的に安定しない(Sigmund,

前回のおさらい
社会的ジレンマにおける協力を説明するメカニズムの一つが「間接互恵性」
その善悪の判断は規範と呼ばれ、最も単純な規範はイメージスコアリング(Nowak & Sigmund, 1998)
イメージスコアリング・・・観察している人が、協力していれば善、裏切れば悪
イメージスコアリングは、完全な非協力者による誤差や侵入に弱く、進化的に安定しない(Sigmund, 20

二名の方が、新規に支援者となってくださいましたので、今回はおさらいを多めに書いてから進めようと思います。
私の研究テーマである協力の進化というトピックとは・・・
人間は超合理的な計算結果のもと行動を決定する超合理マシーンであるとする古典的な経済学(古典的ゲーム理論)によれば、協力は進化しないはずとされてきました。その理由は、協力(コストを払い、他者の利益となる行動)が社会的ジレンマという

前回の続きから
相互協力は、人間社会を支える重要な基盤です。しかし協力は社会的ジレンマという状況にあるため単体では進化しません。
社会的ジレンマとは・・・
(1) それぞれの集団の成員は、協力または非協力のどちらかを選択できる
(2) 各成員にとって、非協力の選択は協力の選択よりも常に大きな利益をもたらす
(3) しかし全員が非協力を選択した時に得られる利益は、全員が協力を選択したとき

今回から数回にわたって、先日公開されました論文についての日本語解説を書こうと思います。
まずは、今までのおさらいから。
相互協力は、人間社会を支える重要な基盤です。しかし協力は社会的ジレンマという状況にあるため単体では進化しません。
社会的ジレンマとは・・・
(1) それぞれの集団の成員は、協力または非協力のどちらかを選択できる
(2) 各成員にとって、非協力の選択は協力の選択

今回も、先日行われたオンラインイベント・アカデミスト学会で私が発表した内容について、寄せられたコメントとそれに対する私の回答を共有したいと思います。(非公開情報です。)
尚、私がアカデミスト学会にて発表したスライドを公開していますので、そちらも併せてぜひご覧ください。下記のURLです。
https://www.slideshare.net/ssusere6c2ff1/ss-232291179?q

0人が支援しています。
(数量制限なし)