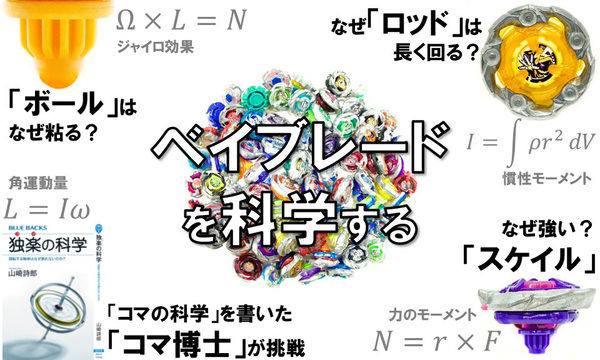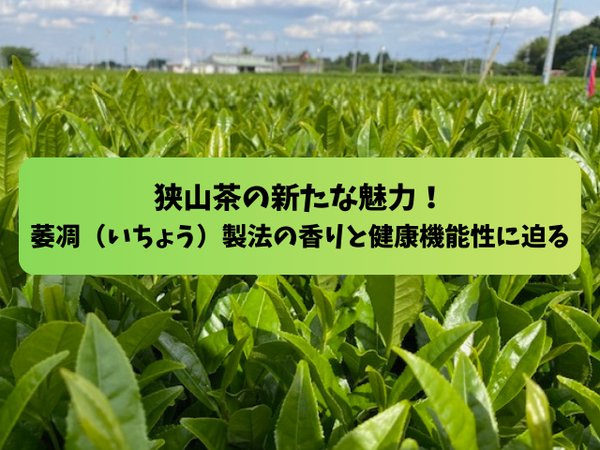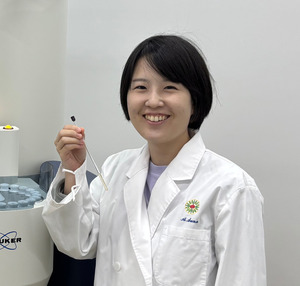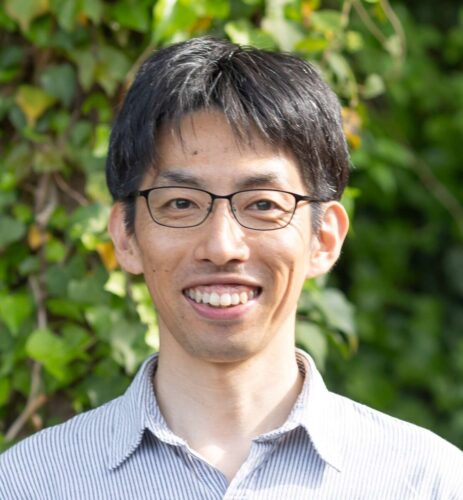
Challenge period
2022-11-01 - 2027-10-31
Final progress report
Fri, 30 Jan 2026 20:05:13 +0900
Progresses
70 times
Supporters
35 people
Elapsed time
Tue, 01 Nov 2022 10:00:00 +0900
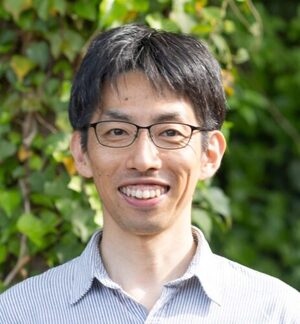
#46 寄付の根本問題と、寄付募集の根本問題
今年度は、幸いにして常勤の特定准教授として大学で研究できる環境があります。
といっても、多くの教員の方々が担われている「教育と研究」という役割ではありません。
「実務と研究」を行う立場にあります。
ですから、やはり実務にとってインパクトのある研究をしたいと考えています。
実務にとってインパクトを生む研究には、「そもそも論」に立ち返るようなテーマが重要です。
言い換えれば、根本問題に取り組むということです。
私が特に『寄付白書』などに取り組む中で感じるのは、寄付に関する不安感が根本問題の1つであるということです。
・「寄付したお金がきちんと使われているのか不安に感じる」という人は、直近の1年間で寄付したことのない人のうち、81.2%(寄付白書2021)
・「寄付したお金がきちんと使われているのか不安に感じる」という人は、直近の1年間で寄付した人の中でも、72.0%(寄付白書2021)
ということが示されています。
寄付をしている人も7割以上が不安である、というのは、どう考えてもまずい。
寄付を預かるファンドレイジングという仕事をしている者として、重大な問題だと考えています。
これに対して手を打つことは、非常に重要だと思うのです。
寄付が安心してできる、ということを実現する。
これは、寄付の根本的な課題を1つ取り除くことになると考えています。
一方で、寄付募集(ファンドレイジング)の根本問題については、どうでしょうか。
実務者として、また助言者として非常に多くの組織を見てきて、根本的な問題は
「ファンドレイジングのテキストを読んでも、アドバイスを受けても、自分の団体では忙しかったり周りを説得できず、それが実施できない」
という点にあると思っています。
言い換えれば、寄付募集への組織的な投資ができないということです。
ファンドレイジングはマーケティングと同様に組織行動であるわけですが、マーケティングも同様の問題を抱えてきており、近年は研究の蓄積もあります。
https://journals.sagepub.com/doi/10.1509/jm.15.0417
ただ、マーケティングにおいてはアナリティクス(市場、ターゲット、施策などの分析)によってマーケティング投資の価値を事前に分析する、というアプローチが多いです。
日本のファンドレイジングは、そのような分析をできている組織は非常に少数です。
(そもそも米国でも、多くの団体のリーダーがファンドレイジング戦略を持っていないと指摘されています)
https://www.compasspoint.org/underdeveloped
ある組織において他の活動(例えば現場での受益者支援)には時間や資金などの資源を動員でき、ファンドレイジングには資源を動員できないというならば、それはファンドレイジングの個別技術以前の問題です。
この根本問題を解決しない限り、その団体にとってファンドレイジングの個別技術の話は(勉強にはなるでしょうが)意味があるでしょうか。
残念ながら、その技術は実践されず、ファンドレイジングに関する組織のパフォーマンス(寄付額など)を改善することにはつながらない、ということになります。
じつは寄付と寄付募集の根本問題は繋がっています。
・寄付者が寄付の使途の明確さを求め間接費を嫌うこと(できることなら、寄付は全額が活動に使われてほしい、広告宣伝や寄付募集には自分の寄付を使わないでほしいと考えること)
が、
・寄付募集に使える資源(資金など)の不足
を招いているということが指摘されています。
https://ssir.org/articles/entry/the_nonprofit_starvation_cycle
この問題を解決するには、
・寄付の透明性を高め、安心感を生み出す
・寄付募集の組織づくり、組織的な投資のメカニズムを明らかにする
という2つのことが必要だと考えており、特に後者は科研費のテーマとも強く関連するので、今年度からしっかり研究をしていこうと思います。
また、このような根本問題にチャレンジしたい、という人とも(実務者・研究者などの境界線を越えて)交流していければと思っています。
Unsplashのserjan midiliが撮影した写真