



橋本幸士さんの講演会を開催いたします(Zoom・無料)。ぜひご参加ください!
「宇宙を支配する数式」
橋本幸士(京都大学・教授・素粒子論(玄理論))
・日時:2024年7月30日(火)19:00 - 21:00(開場18:45)
・場所:Zoom meeting room
・参加方法:下記ページから参加登録願います。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc9_fSDwyk7rDm0CksN9G1l4Ntrmb4fkGfMjLk8uNKno_6Sw/viewform
登録者に講演会のZoom URLが送信されます。
素粒子は行動抑制ネットワークを備えるか?みなさんご一緒に議論しましょう。


研究計画の第2弾、「素粒子物理学に関する専門家との対面議論」を実施しました!
・専門家:橋本幸士さん(京都大学・教授。量子重力、弦理論、機械学習、理論物理学)
・日程:6月21日(金)13:40-
・場所:理学部5号館 509号室
橋本さんのご研究室を訪ね、じっくり議論しました。
弦理論では、素粒子に「構造」を想定できる可能性があります。すなわち、BINを想定できるかもしれません。
7月には、オンライン公開研究会を開催します。
果たして、心のBIN仮説は、素粒子に対し適用可能なのか。
橋本さんのご研究内容も、もちろんじっくりお話いただきます。
https://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~koji.hashimoto/aboutMe.html
みなさん、ぜひご参加ください!
日程や参加方法を、後日公開します。


石を焼成する彫刻家、伊勢崎寛太郎さんのオンライン講演会の録画を公開します。
なぜ焼くのか。焼かれた石はどうなるのか。
石や土に秘められた内面を引き出すための試行錯誤を、芸術家が生の声で語ってくれます。
大変貴重な内容です。伊勢崎さんの思慮深い語り口が、魅力的です。
動画はこちらからどうぞ。
https://mind-of-matters-lab.com/cloud_founding_1st_invited_lecture/


大変有意義な講演会になりました!
焼成により石に内在する時間や他者性を導き出す。
それは石に内在するBINへのアプローチ法の一つだと納得できました。
伊勢崎さん、参加者のみなさま、ありがとうございました!


伊勢崎寛太郎さんのご講演、あさって5/29/19:00開始です。
なぜ石を焼成するようになったのか。
石の新奇性を引き出す「創作」に至る過程を、語ってくださいます。
創作=「狙ってもできないことを、狙う(太⽥洋輝氏)」方法論とは?
ぜひご参加ください!
参加登録(無料)はこちら:https://mind-of-matters-lab.com/isezaki_lecture/


石を焼成し、石の新奇性を引き出す彫刻家、伊勢崎寛太郎さんの講演会を開催いたします(Zoom・無料)。ぜひご参加ください!
「自然物に内在する未来の時間」
伊勢崎寛太郎(東京造形大学・助手)
・日時:2024年5月29日(水)19:00 - 21:00(開場18:45)
・場所:Zoom meeting room
・参加方法:こちらのページから参加登録願います。
モノの心の研究会・伊勢崎さん講演会
登録者に講演会のZoom URLが送信されます。
石の心=行動抑制ネットワークについて、みなさんご一緒に議論しましょう。


みなさま、どうぞ下記からご覧ください。
お待たせいたしました。
モノの心の研究会の活動にご注目ください!


4月になり、プロジェクトの活動が始まりました。
みなさんにお約束した研究計画のうち、第1弾の概要が決まりました!
「石に関する専門家との対面議論」
・専門家:伊勢崎寛太郎さん(石の芸術家・東京造形大学助手)
・日程:5月8日(水)
・場所:東京都内
伊勢崎さんの制作現場を訪ね、じっくり議論します。
石を高温で溶かして作品を仕上げる伊勢崎さんは、「石に余計な行動の解放を促す想定外の状況」をご存じだと期待しています。
どのような議論になるか、今から大変たのしみです。
5月末頃には、伊勢崎さんを招いて、オンライン公開研究会を開催します。
みなさんもぜひご参加ください。日程や参加方法を、後日公開します。
モノの心の研究会のHPは、現在制作中です。4月末には公開される予定です。
伊勢崎さんとの議論のまとめを、「活動報告」へアップします。お楽しみに!


みなさま、ご支援、ご協力ありがとうございました!
早速、今後の予定の詳細を決め、研究を進めていきます。
オンライン講演会のURLはその都度公開しますので、みなさまぜひご参加のうえ、一緒に議論をお願いいたします。心のBIN仮説がどれくらい広がるかたのしみです!
今後も私たち「モノの心の研究会」に興味をもっていただきますよう、よろしくお願いいたします。

SSL encryption communication is used in this Web site, and the informations filled out are safely transmitted.
お礼のメッセージ and others

2
supporters
back
(No quantity limit)
研究会HPにお名前掲載 and others

10
supporters
back
(No quantity limit)
研究会レポート謝辞、配信動画クレジットタイトルにお名前掲載 and others

17
supporters
back
(No quantity limit)
研究会での質問・コメント優先権 and others

0
supporters
back
(Limited to 12)
論文謝辞にお名前掲載 and others

4
supporters
back
(Limited to 10)
個別ディスカッション and others

0
supporters
back
(No quantity limit)
出張講義 and others

0
supporters
back
(No quantity limit)
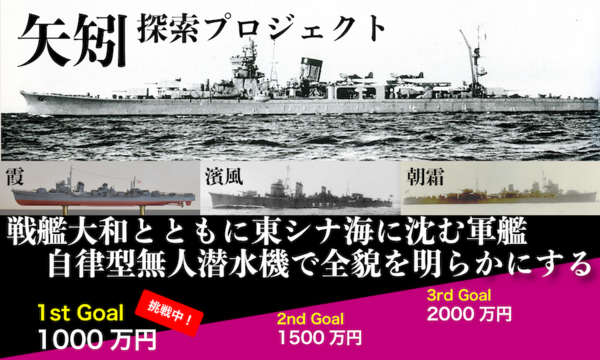




Research activities after crowdfunding
2025-03-05 Other Impact クラウドファンディングで講演を依頼...
2024-12-12 Media Appearance / Lectures 「ダンゴムシに心はあるのか?大学だからこそ、追究できること」
2024-12-09 Media Appearance / Lectures 触角にチューブを装着されたダンゴムシの感覚を想像する
2024-11-12 Media Appearance / Lectures 境界のほつれと行動抑制ネットワーク
2024-11-11 Research Output Turn repetition in pill bugs
2024-11-09 Media Appearance / Lectures 動物のわからなさと行動抑制ネットワーク
2024-09-16 Media Appearance / Lectures 「ダンゴムシに心はあるのか?大学だからこそ、追究できること」
2024-08-02 Media Appearance / Lectures ダンゴムシ教室