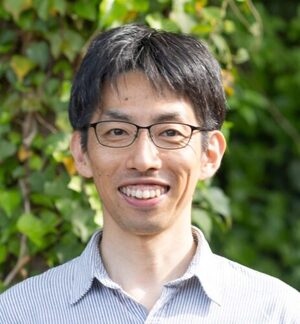Machii Nagatoshi
Challenge period
2023-09-05 - 2025-03-31
Final progress report
Tue, 18 Mar 2025 15:23:51 +0900
Progresses
24 times
Supporters
21 people
Elapsed time
Tue, 05 Sep 2023 10:00:00 +0900

外にないものを生み出す、外に潜在的にあるものを発見する 〜第1話〜(阿部)
どうも阿部と申す、第二弾なり。
今回は、「京大発 専門分野の越え方―対話から生まれる学際の探求」という本の
第3章:専門分野の底流にあるものとしての<学際> のパートを扱い、メンバー3人で読書会を行った。その議論の中で生じた自分の違和感を今から記す。
3章の筆者である萩原氏は、総人のミカタというFDの役割も担う異分野交流プログラム(と私は捉える)における<学際(=infra-disciplinary)> を「専門分野同士のみえない依存関係を顕在化することを通して、自己の専門分野とは何かを問うこと」とまとめている。またその過程で、自分の専門分野のよき案内人になることや、異分野の特質を適切に測量する能力を育まれることが期待されている、という(p46)。
阿部はこの<学際>の考えに対して、我々が考える異分野交流とは少し異なる見方が導入されているのではないかという、違和感を感じた。
どういうことかというと、我々はよく異分野交流ワークショップを設計する際の雑談の中で、「関係性の創発」「アイデア創発」「創発的コラボレーション」「リフレーミング」「創造性」といった言葉が出てきたりするが、どれも何か予定説的に外に答えがあるものを引っ張り出す、というよりは、外にない新しいもの(関係性)を生み出しているという側面が強い言葉群な気がする。
一方で、本書の「専門分野同士のみえない依存関係を顕在化」という言葉や「よき案内人」「適切に測量する」という言葉の選び方は、まるで外に確定的な地図やネットワークが存在しそれを取り出す、といった考え方で語られているという印象がある。
単なる言い方の違いなだけなのではと、この違和感を一蹴することもできるが、なぜかこの違和感が阿部の中に止まり続けてしまうので、この違和感を起点にもう少し粘土をコネコネさせていただきたい。(次回へ)

0 supporters back
(No quantity limit)

0 supporters back
(No quantity limit)

0 supporters back
(No quantity limit)