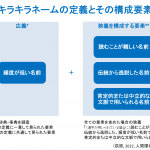大学はもう死んでいる?- 東京大学・吉見俊哉教授
都市論や文化研究を専門とする東京大学・吉見俊哉教授。大学の現状に危機感を抱いた吉見教授は、大学を再定義すべく、その壮大な歴史をたどる『大学とはなにか』(岩波書店、2011)を著した。その著書によれば、大学は「二度目の死」を迎えているという。出版から7年、2015年の「文系学部廃止」にまつわる一連の報道や「デジタル革命」のさらなる進展などいくつかの変化を経験したなかで、あらためて大学のこれまでとこれからについてお話を伺った。

※吉見教授は2020年4月25日(土)開催オンラインイベント「ポストコロナ時代の大学論」に登壇予定です。
——『大学とはなにか』では大学の歴史の見取り図を示す仕事をされました。今存在する大学は、一度衰退して生まれ変わったものであることを知り、驚きました。
まず大学はいつ頃誕生したのかというと、12〜3世紀頃です。最初は1158年にボローニャ大学、次は1231年にパリ大学がつくられました。ただ大学は、そのあと一度死んでいるんですよね。大学が一度価値をなくしている時代があるんです。16世紀から18世紀にかけてのことです。私たちが高校までの教科書で習ったような思想家や科学者、たとえばデカルト、パスカル、ライプニッツたちが活躍した時代です。
当時、大学の教授職であること=偉いというわけではありませんでした。知的に権威を持っていたのは、アカデミーの会員や非常に高く評価される書物を書いている人物でした。知の基盤を支えたのは出版とアカデミーだったのですね。大学はすでに時代遅れだとみんなが思っており、中世の大学はそこで価値を失いました。19世紀になると第二の大学が復活してきます。まずはこの大きな流れを捉えることがとても重要です。
——中世に第一の大学が誕生し、19世紀になって第二の大学が誕生するのですね。それでは、まず中世の大学とはどのような大学だったのか、教えていただけますか。
第一の大学は基本的にはヨーロッパ中世の商業的なネットワーク、中世都市のネットワークに支えられていました。ヨーロッパ中世の経済が10世紀頃から復活しますから、商人や聖職者、知識人たちが都市から都市を渡り歩いていくことになります。学生も教師も同様でした。ただ旅人は地付きの権力構造を持っていないので立場が弱いんですね。各地の領主から干渉されるわけです。そのときに学生と教師が協同組合みたいなものを作って、私たちはローマ教皇、あるいは神聖ローマ皇帝から特許状をもらっていると言い張る必要がありました。その協同組合を彼らはウニベルシタス、今でいうユニバーシティーと呼んだ。それでイタリアに始まった大学はキリスト教の体系のなかでヨーロッパ中に広がって行きました。
——そのようにして広がった大学はやがて危機を迎えるのですね。何が要因だったのでしょうか?
16世紀に起きた印刷革命が一番の要因だったと思います。それまでは写本しかないので、一冊の本を見るためには何か月も旅して、その本があるところに行かなくてはいけませんでした。それ以上に、本の知識をたくさん蓄えている大先生が各地にいて、その先生の教えを請うには、その先生がいる街まで旅していく必要があったのです。
しかし、印刷革命によって、同じ情報を持ったひとつの書物が何千部何万部と流通しうるようになってしまいました。ある種の情報爆発が起り、情報へのアクセシビリティが決定的に変わります。それまでは相当の労力を払って旅していたのが、本を買って読むようになる。
——既視感があります。
そうです、これは21世紀に起こったことと非常に似ています。現在私たちが経験している情報爆発は21世紀にインターネットによって起こったのが最初ではないんです。16世紀に出版というものを通して、最初の情報爆発が起こっているんです。大学もその影響をかなり受けました。17世紀の最先端の知を支えたのは大学にとって代わった出版でした。
ちなみに、この変化を見事に活用したのがコペルニクスだといわれています。コペルニクスが地動説を唱える前に、それほど重要な天文学上の発見は起きていないそうです。ただ、コペルニクス以前とコペルニクス以降で違うことは、彼が印刷革命の洗礼を受けた最初の人だということです。
彼がそれ以前の天文学者と違ってできたことは、ヨーロッパ中から印刷という形で発行されている天文学上のデータを一箇所に買って集めることでした。いろんなデータを集めて比較参照すると、どう計算しても天動説は成り立たない。教義には反するけど、この公式でしか説明できない、というところまで行き着きます。これは比較参照するデータがたくさんあったからこそできたことです。いまのビッグデータと基本的には同じ話です。
——コペルニクス的転回がこれから起こるかもしれないといった点ではわくわくしますね。出版システムが大手を振るった後は、大学には何が起こったのでしょうか?
そこで完全に死に絶えてしまったら、大学というのは残ってないわけです。19世紀になるとドイツで復活してきます。ドイツはナポレオン戦争で負けますね。ドイツは比較的大学が残っていたため、大学を核にして新しいドイツの知や学問を立て直そうという動きが、フンボルトという人を中心にして起きました。
それまでの大学はすでに確立した教義を先生から学生に教えるだけでした。しかし、フンボルトは研究と教育の一致ということを言い出します。文系の場合はゼミナール、理系の場合は実験室を主体として、学生と先生が一緒に学びながら同時に研究する新しい仕組みを整え、大学を再構築しようとし、ベルリン大学で実現していきます。これが功を奏し、新しい大学のモデルになります。これは、勃興期のプロイセンが国民国家として大学を支えていたため可能になったことです。この新しいモデルが大ヒットして、その後19世紀以降、20世紀後半までの第二世代の大学の基本モデルになります。
——ゼミに実験室、私たちは基本的にその延長線上にいるのですね。そして、またその線が切れそうだと……。
20世紀末に再び大学は世界史的な危機に至ったと思います。これには量的な危機と質的な危機と両方があると思います。量的な危機は簡単で、あまりにも大学が増えすぎてしまった。全世界で大学は1万8000くらいあるといわれています。
質的な危機でいえば、デジタル情報革命が起きて知のあり方が決定的に転換しました。16世紀に印刷革命が起こって情報のアクセシビリティがまったく変わってしまい、それまでの大学が価値下落を起こし、新しい出版システムのなかで新しい知がどんどん生まれてきた。さらにいうと、16世紀という時代は大航海時代であり、世界中が銀によって繋がっていった最初の劇的なグローバリゼーションの時代でもあります。現代を生きる私たちもデジタル情報革命とさらなるグローバリゼーションとを経験している。今の私たちの時代というのは16世紀の状況にとても似ています。

——大学はこの危機を乗り越えることができると思いますか。
そのためには少なくとも大学の再定義が必要だと思っています。第一世代の大学は都市ネットワークの大学、第二世代の大学は国民国家の大学でした。第三世代の大学は、やはり「地球社会の大学」になると思います。地球社会の知とはいかにあるべきかについて考えなくてはならない。この新しい地球社会の知も、目的遂行的な知と価値創造的な知の両方が必要だと考えています。
目的遂行型の知が向かう方向ははっきりしていて、国連の持続可能な開発目標(SDGs)が示す17項目にもあるような環境問題などグローバルな課題を解決するために知を組み合わせていくことです。他方で、それを支えるために、「グローバル・ヒストリー」のような地球社会の新しい歴史、あるいは新たな思想や倫理も求められると思います。今までの哲学や歴史学は、基本的には「日本の」思想や「日本の」歴史など、国民国家で区切られていました。そうではなくて地球社会にとっての歴史とはなにか、哲学とはなにか、ということを問わないといけなくなるのではないでしょうか。
——そうした危機のなかでも、よく議論の俎上に載せられるのがいわゆる「文系」の学問です。先生が数年前に書かれた『「文系学部廃止」の衝撃』(集英社新書、2016)のなかでは、「文系は役に立つ」と言うべきであるという主張をされていました。「文系」の学問の未来についてどう考えていますか。
その本では、まず最初に文部科学省は文系学部を廃止するとは一言も書いておらず、マスメディアが読み違えたものだと指摘しました。多くの誤解に基づき議論がなされていたんですね。しかし、その議論があれほど盛り上がったのは、文系学部はもう不要ではという潜在的な危機感が世の中にすでにある程度流布していたからではないかと思います。さらに、その背景には文系の知識というのは、教養としては大切だけれども役に立つ学問ではないのでは、という空気があったと思います。
実際に、たとえば文学部系の学部で教えている先生方のなかにも文系の知は役に立たないけれども大切だ、という人がいます。私はその議論に異論があります。私は文系の学問は絶対に役に立つと思っています。というのも、役に立つということ、有用性には2種類あるからです。ひとつは「目的に対する手段として役に立つ」という、目的遂行的な有用性。つまり、東京から大阪まで、あるいは月まででも結構ですが、どこかにもっとも速く行くうえでの有用性などですね。これは特に工学系が得意です。
——となると、もうひとつの有用性は何になるでしょうか? 先生が大学の歴史を俯瞰した試みも、その答えと関わってきそうです。
もうひとつの有用性は、価値を創造する、つまり目的そのものを創造するという意味になります。たとえば1960年代の日本では「より速く、より高く、より強く」のような価値がすべてだと思われていましたが、今の私たちは必ずしもそう思っていない。今は循環型社会やサステナビリティが大切だと考えるように変わってきました。時代によって価値は変わるのです。目的遂行的な有用性は、目的が決まったなかでは最高の結論を出しますが、与えられた目的に対してしか役に立つことができないんですね。
この目的を創るためには、私たちが囚われている自明性を一度壊す必要があります。既存の概念を壊していくには、私たちが当たり前だと思っている世界を「内側から」批判していくことが必要です。人類学や歴史学、社会学など人文系の学問はその批判の作業をひたすら行ってきました。この作業は新しい目的とか価値を創造するためには不可欠だと思います。
価値のドラスティックな転換は頻繁には起こりません。でも、長い期間で考えたときに、価値の転換は過去にも起こってきたし、これからも必ず起こると思います。文系は短期的には役に立たないかもしれない。しかし、長期的に社会が転換していく、価値が少しずつ変わっていくときに、その変化を捉えるために、文系的な知識は絶対必要になります。そう考えると、長期的には文系は役に立つんです。
(取材:柴藤亮介、構成・文・撮影:荒井俊)

研究者プロフィール:吉見俊哉
東京大学大学院情報学環教授
東京大学出版会理事長
1957年、東京生まれ。東京大学大学院情報学環教授。東京大学出版会理事長。1976年に東京大学理科I類に入学後、同大学教養学部教養学科卒業。同大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。東大新聞研究所助教授、同社会情報研究所助教授、教授を経て現職。2006~08年度に東大大学院情報学環長・学際情報学府長、2009~12年度に東大新聞社理事長、2010~14年度に東大副学長、同教育企画室長、同グローバルリーダー育成プログラム推進室長、2010~13年度に東大大学史史料室長等を歴任。2017~18年にハーバード大学エドウィン・O・ライシャワー客員教授として同大学で教える。社会学・文化研究・メディア研究専攻。集まりの場でのドラマ形成を考えるところから近現代日本の大衆文化と日常生活、文化政治を研究。主な著書に、『都市のドラマトゥルギー』(河出文庫)、『博覧会の政治学』(講談社学術文庫)、『万博と戦後日本』(講談社学術文庫)、『大学とは何か』(岩波新書)、『「文系学部廃止」の衝撃』(集英社新書)等多数。


この記事を書いた人
- academist journal編集部です。クラウドファンディングに関することやイベント情報などをお届けします。